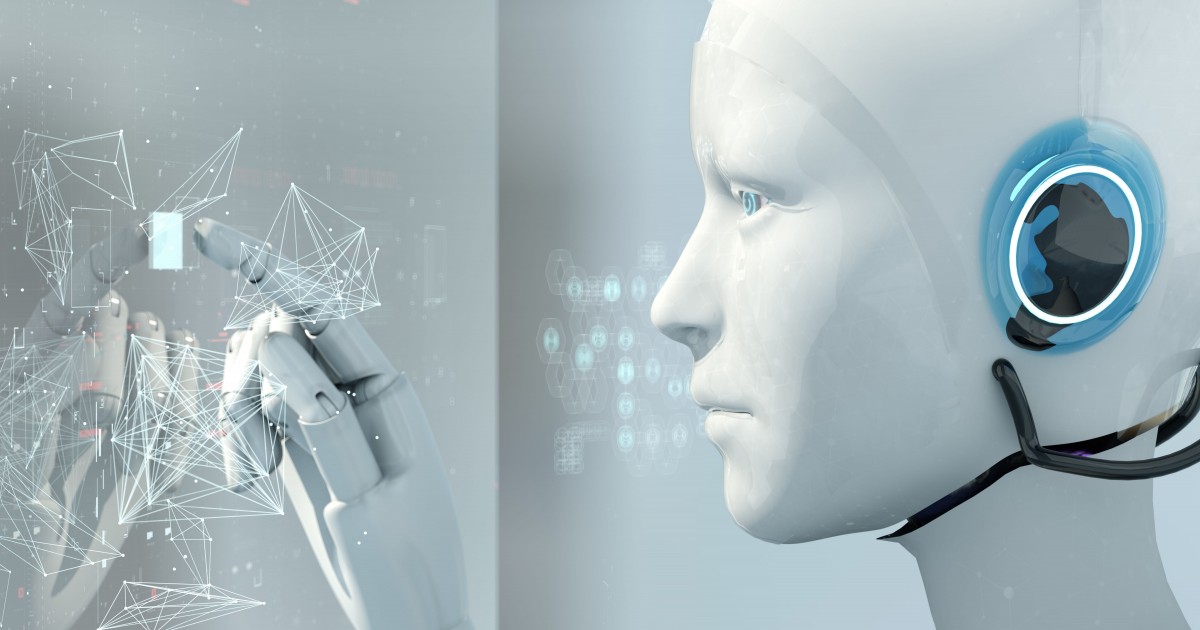月刊BLUEBNOSE 2025年11月号(#23)『WebサイトのDIYはオススメしない』
ビジネスオーナーとしてDIYすべきかどうか、改めて検討するきっかけになれば幸いです。
先日noteでは、『文化も時間が淘汰する』と、「審査」や「評価」の難しさ、自分勝手な甘い物差しは通用しないとお伝えしました。
その中ではあえて取り上げませんでしたが、専業でない方によるお手製のプロモーションやマーケティング施策についても、同様に厳しい物差しが適用されます。
コストを削減したいという事情や、「やってみたかった」という想いを否定するつもりはありませんが、第三者に働きかけ、時間やお金を少しでも割いてもらおうと思うなら、守るべき最低限のラインがあると考えています。
そこで今回は、「あくまでも趣味の延長だから」という甘えに対して、更に厳しい指摘を加えようと思っています。ノーコードツールの充実やAIのサポートによるローコードでハードルが下がったからこそ、サプライサイドとしてどうあるべきか、改めてお伝えします。
「やりたい」=容認ではない
皆さんが何かを「やりたい」と思うのは個人の自由です。興味を持ち、挑戦してみたくなる気持ちは「素晴らしい」の一言です。
ただ、「やってみたい」からと言って、それを免罪符に「何でもやって良い」とはなりません。
例えば、テーマパークでゴーカートを楽しんだからといって、免許も持たずに公道で運転することは許されません。スマートフォンが普及し、画像加工や映像編集も手軽にできるようになったからといって、他人の肖像権を無視した盗撮や、サブリミナル効果を狙った編集や、激しい点滅を伴う視覚効果、画面酔いを引き起こす動画、さらには緊急地震速報やJアラートの乱用も御法度です。著作権を無視した音源の使用も同様に、決して容認されません。
企業秘密や国家機密をみだりに撮影・記録することも許されません。「ご遠慮ください」と注意書きされている場合、録音・録画のルール違反やマナー違反も、例外ではありません。
書店や動画投稿サイトには参考書やハウツーコンテンツが溢れ、ホームページビルダーやAdobeのソフトなど、趣味や遊びとして興味深いものも目白押しです。やってみたくなる気持ちはよく分かりますが、それがあるからといって、何をやっても許される訳ではありません。何でもやって良いのは、特別な許可を得た環境や学校、サンドボックスの中のみに限られます。
私的利用や教育目的の範疇を超える場合は、法令やルール、自主規制やマナーを守る必要があります。それが、最低限の原理原則です。
電波を発する無線機や、電気通信設備に接続する通信端末であれば、認可を受けて技適マークを取得する必要があります。繰り返し充電可能な蓄電池なら、消防法(危険物としての貯蔵・運搬規制)や電気用品安全法(技術基準による安全性確保)を守らなければなりません。
建築物であれば、接道義務や建蔽率、耐震性などの建築基準法を守らなければ、建て替えすら認められません。原動機付きの二輪車や自動車は、運転者が免許を持っていたとしても、法律に定められた保安部品が揃っていなければ、公道を走ることはできません。
DIYや趣味の範疇出会っても、公共の場や社会で生きていくためには、公序良俗や社会通念上、相当と思われる基準を守る必要があります。
Webサイトやチラシ、メルマガはただのアートじゃない
法律を守るのは当たり前、と思われるかもしれませんが、念のために指摘しています。
ただ、Webサイトやブログ記事、個人で配るチラシやメルマガについても、守るべき基準やセオリーがあると分かっている方は、どのくらいいらっしゃいますか?
個人の趣味で葉書に絵を書き、それを私的な通信として誰かに送ったり、アートとして個展を開くのと、広告やDMのつもりで特定の誰かに送付する場合とでは、意味も性格も全く異なってきます。
完全なアートや、誰にも迷惑をかけない個人的な楽しみであれば、モチーフや著作権、表現規制を気にする必要は一切ありません。しかし、これを自らの作品として発表する場合や、他人の生命や財産、名誉に影響を及ぼす場合、自由として認められる範囲は格段に狭まります。
これが、マーケティングや宣伝広告、プロモーションを意図したものであれば、なおさら「ただのアート」として好き勝手にやって良いものではなくなります。優良誤認や誇大広告はもちろん、近年ではステルスマーケティングも対象となるなど、規制は厳しさを増しています。そのため、景品表示法はもちろん、薬機法を遵守した表現へ書き換えを求められる場合があります。
また、個人情報保護法や特定電子メール法といった法律もあり、「やっても良い」と容認されていたものが、専門家でも把握が困難なレベルで徐々に狭まりつつあります。
誰かの元に届いて、感情の変化や行動を誘発する以上、発信した側、仕掛ける側としては一定の責任が発生します。それにも関わらず、「何をやってもいい」とDIYや趣味の延長で素人判断で適当にやり過ごしてしまうのは、社会や市場に対して、あまりにも無責任ではないでしょうか。
完全な密室での私的利用なら、どんなにアンモラルかつ過激なエログロ描写も全く問題ありません。しかし、それがチラシの裏の落書きであったとしても、一度流出してしまうと、表現者や流通に関わった人が何らかの処罰を受ける可能性が生まれます。
アートだからといって、全てが「表現の自由」として認められることはありません。Webサイトやチラシ、メルマガのように、宣伝や広告の側面を持つものは、なおさら「完全な自由」ではない。
よって、「やってみたかったから」と挑戦するのは素晴らしいことですが、周りを巻き込んだり、誰かを傷つけるような行為は十分注意しましょう。
ハウツーレベルと使えるレベルの差が大きい
スケッチやデッサンのような芸術分野も同様ですが、Webサイト制作やプログラミングの世界では、教科書や参考書を最後までやり切ったからといって「実践」レベルに到達できる人はごく稀です。
「実践」の課題やタスクが次々と降りかかり、「出来なければ困る」状況にでも陥らない限り、「できる」や「使える」レベルにはなりません。
スケッチでも、大まかなアタリをつけたり、外形を取るところまでは教本通りにできたとしても、そこから完成見本との差が大きく、「その間を知りたい」と思う方は多いのでは。
参考書がある、ハウツーコンテンツが豊富にあるーーそれでも「言われた通りやる」ことすら難しい。学んだ後の具体的な目標が定まっていなければ、「一通り学んだのに何も身につかない」まま終わるでしょう。
今日明日、自分が食べる料理ですら、レシピを「そっくり真似る」ことが難しいのに、習得までに時間がかかり、要求される水準も高いWebサイト制作やプログラミングが、座学やオンラインスクールだけで身につくはずがありません。
一も二もなくどこまでも実践の世界では、本やハウツーを片手にDIYしても、そう簡単には役立ちません。よって、それを本業として生きていく覚悟がない人には、全くもってオススメしないというのが正直なところです。
秒進分歩の世界で、最新でも古い
Webサイト制作やプログラミングの世界で、DIYをおススメしないもう一つの理由が「時間の速さ」です。たとえ最先端の書籍であっても、わずか1年半〜2年で古くなってしまう世界。
参考コードを用意し、原稿を整えている間に、企画当初は最先端だった技術が、出版時にはすでに時代遅れとなっている。それが当たり前の、秒進分歩の世界です。
出版の早い電子書籍なら大丈夫、と思うかもしれませんが、そう単純ではありません。ハードやOSの更新、技術的トレンド、社会的な変化が早すぎるため、「書いてある通りにやったのに動かない」ことも珍しくありません。
ましてや、これからDIYで学ぼうとする人が、どの本やコンテンツが最新なのかを見極めるのは至難の業。どの執筆者が信頼できるか、どの出版社が正しいのかーーそういった判断も、難しいでしょう。
中には「昔からホームページビルダーを使ってみたくて」と、TABLEタグやFlashを駆使した懐かしいWebサイトを作りたい人もいるかもしれません。しかしながら、世間のトレンドやユーザーの感性、利用環境は今も最先端を追いかけて変化し続けています。
そういった変化を踏まえ、客観的な目で「今後を見据えると、これがベスト」と判断できるでしょうか?専門家でさえ、枯れた技術や古い発想から抜け出せずにいる状況です。今から学び始める人にとっては、なおさら困難でしょう。
AIだって、セオリーや法令を知っているとは限らない
ノーコードが豊富な時代。ましてやAIもあるんだから、AIと共にローコードで進めればいいーー。それも一理あります。
しかし、ノーコードツールやAIが、Webサイトとして押さえるべきセオリーや法令を必ずしも理解しているとは限りません。
例えば、自前のWebサイトやGoogleフォームでお問い合わせを受けたり、アンケートを実施する場合、本来であればプライバシーポリシーを掲げるべきですが、それすら見当たらないサイトやLPを数多く見かけます。
通販機能を持たせているのに、「特商法に基づく表記」を掲げていないWebサイトも珍しくありません。Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを導入している場合も、本来はプライバシーポリシーとして明記し、オプトアウトURLを言語や国ごとに用意する必要があります。
利用規約として、対象ブラウザやJavascriptに関する言及があるにも関わらず、本来は触れておくべき著作権や免責事項を定めていないケースも多く、国際的なアクセスが想定される場合は、EU一般データ保護規則(GDPR)や、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)への対応も求められるでしょう。
しかしながら、それらを自動で保管してくれるノーコードツールやAIは、今のところ見当たりません。
つまり、指示するユーザー側に正しい知見がなければ、どんなに優秀なAIであっても「何が必要か」を正しく判断することはできないということです。
SEOやPageSpeed Insightsなどのパフォーマンスに関する項目も同様で、ノーコードツールやAIに全てを任せ切るのは現実的ではありません。
ツールがどんなに進化しても、最終的に良し悪しを判断するのは人間です。十分な知識や経験、真っ当な判断力が伴わなければ、客観的に「使える」Webサイトを作ることはできません。
それでも、DIYで何とかしたいと思いますか?
ビジネスオーナーは、ビジネスオーナーであれ
DIYをオススメしない最大の理由。それは、ビジネスオーナーであるならば、24時間365日を自分のビジネスに注ぎ込め、と思うからです。
確かにビジネスが軌道に乗るまでは、資金的な余裕がないかもしれません。投資する先を絞り、自分でできることは自分でやる判断も、時には必要です。
しかし、ビジネスオーナーにとって最も希少価値の高いリソースは、「時間」です。自分自身の人件費をコストとして正しく認識できないと、「節約」のつもりがかえってビジネスの寿命を縮めてしまうかもしれません。
趣味の延長やスモールビジネスだからといって、何でもかんでもDIYにこだわってしまうと、事業が成長しないまま、静かに衰退していくでしょう。適切にアウトソースしておけば、早期の事業拡大や資金繰りの安定、再投資といった複利効果を期待したり、時間の余裕を駆使した様々な打ち手も選択肢として選べますが、DIYで時間を溶かしてしまえば「どうにかしたい」と思っても、残しておいたはずの猶予も可能性も減っているはず。
Webサイトでも名刺でもチラシでも、「私のこだわり」を完璧に表現したい気持ちは理解できます。しかし、それを受け取る世間やユーザーが求めているのは、プロの品質です。ビジネスオーナーの自己満足ではなく、相手や世間がストレスなく受け取れるものが求められます。
市場や顧客が望むのは、プロフェッショナルな仕事や商品です。ビジネスオーナーの承認欲求を満たすためのお飯事には、付き合ってくれません。
コストを抑えるためにWebサイトやブログをDIYし、手探りでマーケティングやプロモーションを試すのも自由です。しかし、その時間と労力をビジネスオーナーにしかできない成長領域へ割り当てた方が、ビジネスは前に進むはず。
ビジネスオーナーがやらなくても、プロに任せてお金で解決可能なことは適切にアウトソースする。それも、ビジネスオーナーとして重要な意思決定です。
独立開業する以上、いつまでも市場や顧客に甘えてはいけません。腹を括って、ビジネスオーナーになる覚悟を持ちましょう。
月額1万円で、前へ進め
私たちが月額1万円で始められるWeb制作サービスを運営している以上、「コスト」はDIYを始める理由にはならないでしょう。それでも、色んなものをDIYしたい気持ちはよく分かります。
DIYなら、誰かがやった成功例が示されていて、それをなぞる安心感があります。これからどうなるか分からないし、どう進めばいいかも分からない自分のビジネスと向き合うより、進むべき道が分かるし、安全な逃げ道にもなる。
でも、アナタがなすべきことは、「アナタのビジネス」と向き合い続けること。そして、そのビジネスを存続させ、成長させること。それが、アナタのビジネスを支持してくれる顧客や市場に対する、責任の果たし方です。
アナタのビジネスへ投資してくれた人に対して、いつでも自分の事業と向き合う人であって欲しい。誰も正解を知らない、アナタだけの茨の道へ、歩み出しましょう。
もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
さて、月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら