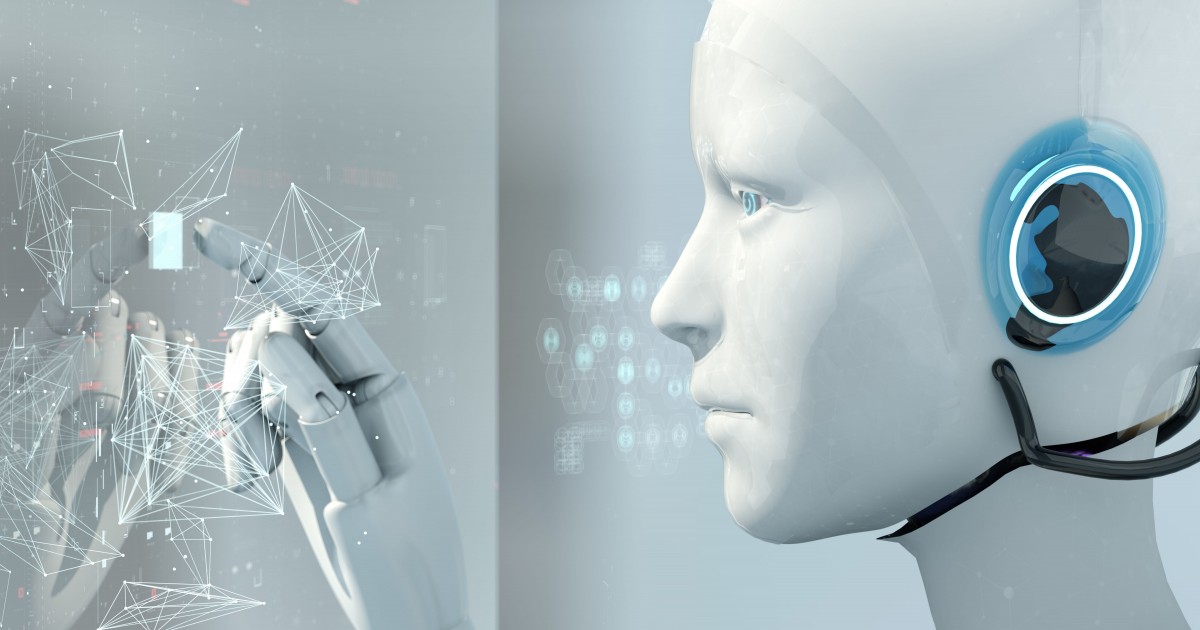月刊BLUEBNOSE 2025年10月号(#22)『形あるモノに囚われすぎるな』
少しでもお役に立つようであれば幸いです。
先日の公開したオウンドメディア、『不動と無常は、常若で』の中で「変えないもの」、継承するものとしての「経営理念」や言語化の重要性に触れました。
「常若」で守っていく象徴としての「コトバ」や、式年遷宮を通じて継承される社殿といった「形」は確かに重要ですが、書かれているテキストや形にばかり囚われてしまうと、それはそれでまた別の弊害を生み出します。
noteでも形や見た目の重要性を取り上げたところなので、
今回はあえて、それらに囚われることの危険性や留意点、アンチテーゼ的な部分について取り上げます。
舌の根も乾かぬうちに自論を否定するような格好になりますが、それぞれの極端なコンテンツを通じてバランスを取るようなイメージで受け取っていただけますと幸いです。
それでは、本題へ入っていきましょう。
遺すためには、日持ちさせる加工が必須
形やコトバに囚われる弊害、デメリット等を解説する前に、「遺す」ため、継承するためにどんな工程が必要なのかを整理しましょう。
食品や資料に共通して言えるのは、腐敗防止のための滅菌や脱水が基本です。保存食作りでも、まずは塩や砂糖を使った脱水から始まって、酢やアルコールを使った除菌、先に麹菌をつけてからの天日干しだったり、燻製などが一般的です。酒類であれば、さらにアルコール度数を高めるための蒸留という手段もあり得ます。
標本の場合でも、肉や内臓といった腐りやすい部位は取り除き、十分な煮沸を経てから、腐りにくく均質な人工物で必要な加工を施します。化石の場合は、さらに時間や圧力が加わり、モヘンジョダロの場合は遺跡を守るために、空気に触れさせないよう埋め戻しが行われました。
いずれにせよ、加工前と加工後とで、見た目や性質は変化します。腐敗しやすい部分や水分は取り除かれ、脂肪や皮膚もやがては分解されてしまいます。古い書物に残った澱粉質、ノリや紙、布ですら紙魚や虫によって食われてしまうでしょう。
最後に残った「変わらないもの」だけを見ても、元の姿が想像できないこともありますし、「遺すため」にあえて強い処理を施すこともあるでしょう。その想いが後の世に汲み取られないことも、よくあるのですが......。
化石だけを見ても、いまだにティラノサウルスの体型や羽毛の量は定まっていませんし、恐竜類の皮膚の色や鳴き声も、ハッキリと分かっていません。化石だけにフォーカスしてみても、トリケラトプスのような角竜類で、トロサウルスやプロトケラトプス、スティラコサウルスといった種が独立したものなのか、トリケラトプスに何かが起きた個体の化石なのか、定期的に右往左往しているような気がします。
現代の変死体なら司法解剖も可能ですが、あまりにも時間が経ちすぎてしまうと、「当時の真相」は闇の中。これは文学やその他の資料も同様で、当時の時代背景や人間関係を踏まえた上でも、真実は分かりません。さらに、当時の資料を偽った書類や詐欺も珍しくありませんし、現代ならよりディープフェイクを駆使して、より本物らしい偽書を作れるかもしれません。
遺ったものだけを見ても全容は分からないし、全てを遺すことも出来ません。また、遺ったものをどう扱うか、どう解釈するかという問題も、必ず付き纏います。それを、忘れないようにしましょう。
血肉などのナマモノは、継承できない
親から子への一子相伝のように、一代限りの引き継ぎであれば、属人性の高い技術や熱のこもった想いなど、目に見える形へ還元しにくいものも継承可能ですが、親子や孫を超えた世代にまで継承したい場合、直接指導可能な範囲を超えて、正確に受け継ぎたい場合、ニュアンスや感覚といった体温や湿度を感じる要素については、継承困難でしょう。
水分が多く、途中で成分が変わったり腐敗しやすい要素、重くて嵩張る部分については、どうしてもリレーする間に抜け落ちて行きます。
だから、相手や時期を問わず、いつでも継承できるようにしたいなら、まずは遺すための作業が必要となります。目に見える形になっていなければ、言語や図式に落とし込み、可視化を図る。それから、時代の流れに耐えられるよう、表現を磨いて水分を飛ばしたり、蒸留を経て濃度を上げ、タルに詰めて熟成させるようなイメージでしょうか。
全てを遺すことは出来ませんが、上手に加工できれば、肉体が滅んだ後も言葉や図式は継承できます。自分より先に言葉や遺すものが腐ったり死ぬことがないよう、しっかり圧力をかけて加工してください。この時、優しさも遠慮も不要です。心を鬼にして、徹底的に負荷をかけましょう。
ただ、とことん脱水し、とことん滅菌して得られた「書き記したもの」や、石のように強固な「形あるもの」であっても、本当に伝えたいことは、そこから滴り落ちた水分や腐りやすい部分、行間や「形に現れない部分」だったりしませんか?
残りやすく継承しやすい「書き記したテキスト」や「形あるもの」だけでなく、もう半分の「抜け落ちる部分」も引き継ぎたいのなら、そこらも視野に入れた残し方、行間や見えないものを想起しやすい形に仕上げましょう。間違って汲み取られないよう工夫するのも、受け継がせる側の責任です。細心の注意を払って取り組みましょう。
テキストや形の継承のこだわりすぎても、腐敗を招く
良質なテキストや形あるものは継承しやすく、誰でも受け取れますが、その手軽さや「見えるもの」にこだわりすぎてしまうと、今度は別の腐敗を招きます。
それは古くから変わらないので、いわゆる「アブラハムの宗教」と呼ばれるユダヤ教やキリスト教、イスラムの諸宗教で偶像崇拝を禁忌としています。場合によっては、イコンや宗教画も禁忌とされます。
その一方で、聖書などの教典だったり、校則や法律といったテキストを絶対視し、「書かれてあるから」と恣意的な解釈によって衝突が起きることも、珍しくないでしょう。責任をテキストに押し付けて、自分はそれに従っているだけというポーズを取ってしまうのは、あまり良い印象を抱きません。
確かに戒律や条文、形は大切ですが、重要なのはそれをどう受け取るか、どう読み解くかです。「そこにないもの」の方が重要なのに、「書いてあること」だけ、「目に見えるもの、手で触れられるもの」だけに囚われてしまうと、正しい解釈も正しい行動もできません。
形あるものは必ず壊れるし、書き記されたものも、行間まで正確に読み取る努力を怠れば、すぐに正しい意味は霧散するでしょう。テキストや形にこだわったところで、それはあくまでも継承しやすいトークンや痕跡であって、全てではありません。
テキストにしたって、教祖が全てを書き記した教典はごく僅かです。哲学書でも同様に、師匠の言葉とされるものは、弟子の仕事であることがよくあります。(例えば、ソクラテスならプラトンが、プラトンならアリストテレスによる言葉が、後の世まで残っている印象です)
イコンや偶像、宗教画でも、書き手や作り手の思惑が、形に反映されています。「別の誰か」による「何らかの意図」が経典や偶像に紛れていても、それらを盲目的に崇拝、信仰してしまうと、元の教義や思惑からは大きく外れてしまうでしょう。
そういったミスリードや、安易なご解釈といった腐敗を避けるためにも、テキストや形にこだわってはいけない。偶像崇拝を禁忌とするのも、そういった事情からでしょう。
継承するのは、背後にある形而上。メタ
式年遷宮で、旧社殿から新しい社殿へ移されるのは、確かに形ある御神体です。ただし、アレは神様が降臨するための依り代であって、神様そのものではありません。長い時間を掛けて一種のモノを継承しているのと同時に、そこから立ち上がる形而上のメタ的なモノも含めて、継承し続けている、と言えます。
目に見える形而下のモノも重要ですし、御神体もみだりに見たり触れてはならない神聖な存在ですが、メタ的な部分がなければ、片手落ちです。両方揃って、初めて意味を成します。
これは、ブランドの理念や企業のパーパスやミッションでも同じでしょう。継承するのは言葉や額装されたスローガンであったとしても、そこに込められた想いや意味、メタ的な行間も正確に引き継がなければ、同一性は担保できません。
「常若」や式年遷宮にならって同一性を保持したくても、守るべきモノを見誤ってしまえば、世代を重ねるごとに、どんどん「別の何か」に変わっていくはず。それでは、市場も顧客も離れていくでしょう。
形あるもの、形而下の「書き記されたテキスト」も大切ですが、それと同様、いやそれ以上に形而上の「目に見えない」メタ的なものも大切。だからこそ、形あるものや、テキストだけに囚われないよう、気をつけたい。
偶像崇拝は禁忌だし、テキスト至上主義、形あるものに囚われすぎるのも禁忌とする。それくらいが、程良いバランスなのではないでしょうか。
形もテキストも、適宜作り替えろ
先人が残したもの、先人から受け継いだものが全てだからと、それに囚われて硬直化するのも、テキスト至上主義の悪癖です。先人の知恵や、「自分たちらしさ」の定義も大切ですが、時代の変化に合わせた適応や、子や孫世代の研究によって、独自の改善方法や革新が生まれるかもしれません。
そこで、「書かれてあるもの」に囚われてしまうと、時代についていけなくなったり、新たな可能性をドブに捨ててしまうことになります。コーランを厳格に守るイメージがあるイスラム教ですが、ハラルが用意されておらず、与えられた選択肢の中で選ぶしかない場合は、禁止されているモノも食べていいと、個々人によって超法規的な運用をすることもあるので、柔軟に「上手くやる」方が賢明でしょう。
いつでも柔軟に書き換え、形を変えながら運用し、時代に合わせながら継承していく。 gitのように、ヒストリーを残しながら分岐や改善を重ね、必要ならいつでもロールバックしたり、原点に戻れるようにしておく。
そうして、視野も思考も狭く硬直化させず、視野を広く保って、柔軟かつしなやかに対応する。それもまた、「常若」から見えてくる大事なコンセプトです。
メタの容れ物と中身で1セット
空っぽな器と、そこに注がれる何か。器の方は適宜作り替え、中に入るものと共に引き継いでいく。
中空構造のまま、どちらも伴っていることが、「常若」や日本の神話から分かる大切なこと。
行間や見えないモノも大切にするBBNと、Webサイト制作やマーケティングに取り組んでみませんか?
また、もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
さて、月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら