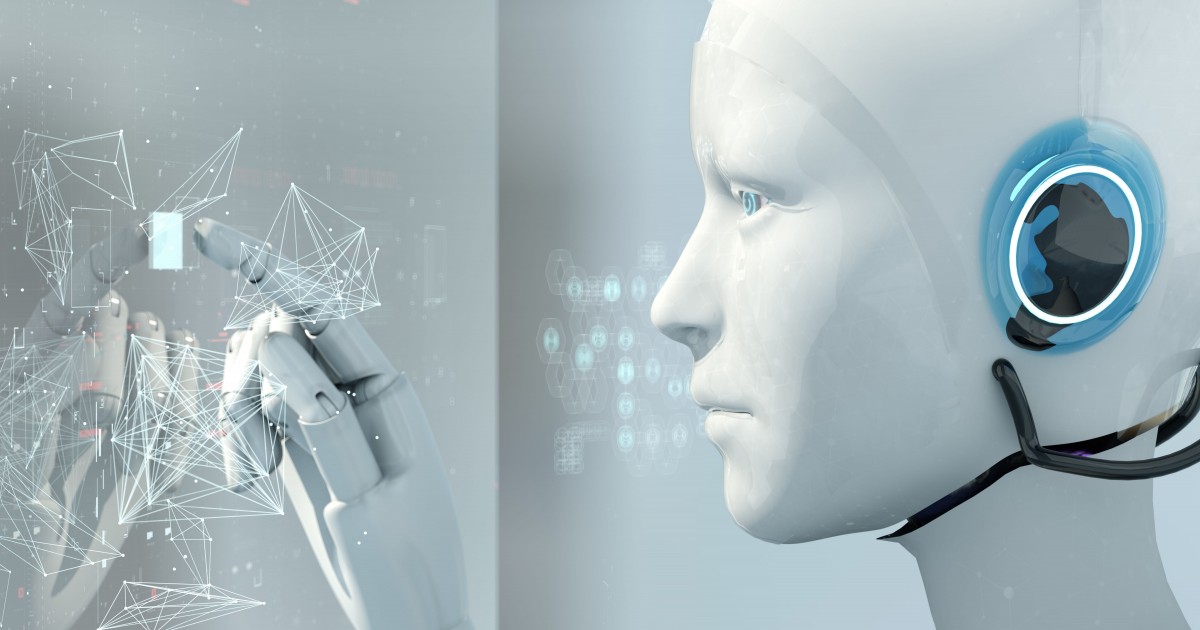月刊BLUEBNOSE 2025年09月号(#21)『正しさより、弱さや間違いの味方で在りたい』
お役立ちコンテンツにはなりませんでしたが、それでも誰かのお役に立つようであれば幸いです。
「三つ子の魂百まで」とはよく言ったもので、幼少期に気が合った友達と、大人になってからも似たような人と関わることが多い、と思ったりしませんか?
私の場合、どちらかというと内向的で温和な早生まれ系男子だったので、体育会系のような押しの強さはないものの、優しさの裏に独自の意見やこだわりと、やや天邪鬼な反骨精神を持つ人を、「類友」として引き寄せがちな気がします。
運動では勝ち目が薄いものの、だからと言って勝ちを譲る気もなく。負けず嫌いを自分の領域で発揮するようなこだわりというか、それ故に文化系であっても安易な迎合も不得意で、むしろ更に反発してしまうようなややこしいタイプ。それも、一癖も二癖もあるような人ほど、親和性が高い印象です。
裏を返せば、男兄弟の中で揉まれてきた「ガキ大将」のような主張の強い人や、典型的な体育会系の文化は昔から苦手で、「先輩や監督が絶対」といった空気や、全員で足並みを揃えるといった雰囲気からは、極力距離を取ってきたように思います。
最近の発信では、例えブランディングであったとしても「やり過ぎ」は控えた方が良いとか、過度に凝ったHTMLやSEO、強すぎる断定や過激な表現についても、避けた方が無難ではないかという記事を発信しています。
例えば、直近公開の記事だと、『SEOも言葉も、程々で』。
強い断定や表現が気になってしまうのは、記事の中身で言及したものだけでなく、幼少期から培ってきた苦手意識も影響しています。
今回は、上記の記事では扱いきれなかった「それ」について取り上げます。なぜ、強い断定や過激な表現を避けて欲しいのか。また、それらと苦手意識がどう関係するのか。順番に解説していきましょう。
正しいと思うから、強く言える
何かを表現するということは、必ず何かに影響を与えます。また、表現の自由には相応の責任も伴うということを理解した上で、それでも誰かに対して強い言葉を投げかけられるということは、発信する側に多少なりとも「自分は正しい」という自負があるということでしょう。
自分の正しさを信頼していなかったり、発信する前提となる部分がグラついているようでは、強い断言や断定表現はできません。自己の表現に対する責任を負うつもりがないのなら、話は別ですが......。
また、発言したい分野や内容に対して、自分がより強く正しいと思っていればいるほど、断定度合いや表現の強さも高まるはず。その分野に詳しい専門家だったり、大規模な自然災害時の気象庁の会見など、慎重な発言が求められる場面であれば、軽率な断定を避け、「〜かもしれない」や「〜の可能性が高いと思われる」と言った逃げ道も用意していることが多いでしょう。
「自分が間違っているかもしれない」とか、自分が信じている「正しさ」に疑いの余地がある、過信できない状態であれば、その分表現の強さは和らぎ、過度の断言も難しくなります。
自分は絶対に間違っていない、自分は常に正しい側に立っていると思い込んでいるから、そうでない人を「間違っている」と糾弾したり、強い批判を平気で浴びせられる。その正しさを過信したり、盲信してしまうところが、個人的には非常に苦手です。
自分への信頼や、正しさに対する向き合い方についても、「やり過ぎ」は禁物。半信半疑で「間違っているかもしれない」という余地も心の中に残しておけば、過剰に強い発言も自然と控えることが可能です。それでも、自分の正しさを強く表明したいと思いますか?
「正しさ」= 誰かの物差し
アナタが基準としている「正しさ」は、何に由来していますか?学生時代に学校で習ったことや、社会人になってからセミナーや書籍からインプットして、身につけた知識やスキルが由来ですか?学術論文や科学的な実証実験、再現性の高いデータですか?それとも、道徳や法律、何らかの経典や戒律ですか?
どれも結局、自分の外にある「誰か」の決めたものであり、それをモザイク状に組み合わせて、「私の正しさ」を作り上げています。自家製100%の「正しさ」は単なる自己中ですし、それでは社会不適合の烙印を押されてしまうでしょう。
ただ、どの「物差し」を採用するか、「誰」の提案を採用するかによっても、総合的な「正しさ」は大きく揺らぎます。様々な宗教の安息日や戒律が異なっていることや、「史実」は年表の上では同じでも、それを解釈した「歴史」について「歴史は勝者が紡ぐ」や「勝てば官軍負ければ賊軍」のように、語り手によって内容や印象が変わることからも、明らかでしょう。
正しくあることに囚われ過ぎてしまうと、「やってはいけないこと」を記載したネガティブリスト形式の刑法や民法といった法律では落ち着かず、「やっても良いこと」を明記したポジティブリスト形式の校則や厳しい戒律でないと、安心できないようになってしまいます。
自由を前提として、部分的な不自由を要求するネガティブリスト、不自由を前提として、部分的な自由を許可するポジティブリスト。前者の方が、モラルやマナーによる自律といった大人としての振る舞いを求めるのに対し、後者は相手を信用しない子供扱いや、強制的な従属が求められている印象があります。
「テキストに書いてあること」を絶対正義としてしまい、思考停止でどんどん縛り付けること、自ら不自由を求めて、動き始めてしまうような気配すら感じます。そこに、「個人の意思」は不要でしょう。
正しさや無謬性を追求し始めると、全体の結びつきは強くなる一方、「個」は徐々に消えていきます。その先に何が待っているか、戦後80年を迎える我々は既に知っていますよね?
自分の頭で考えなくて済む
誰かの物差しや、誰かが考えたこと、書き残したことに全てを委ね、それに合わせて動けば良いとなると、自分の頭を使って考えることも、悩むこともしなくて済みます。ビッグブラザーな「指導者」が考えるから、何かトラブルや悪いことが起きても、ルールや「正しさ」のせいにできる。自分の未熟さを省みることはあるかもしれないけど、基本的には自分が信じた「正しさ」が間違っていたことにできるでしょう。
つまり、何が起きても他罰的、もしくは他責思考が採用でき、周囲に対して攻撃的になりかねません。自分の頭で考えることも減ってしまい、自分の何が悪かったのか、自責に基づく反省や改善、成長の機会も失います。
万が一の事象が起きた場合も、臨機応変な対応など期待できず、いざという時の柔軟性も欠けています。多少の間違いでも許容できないマニュアル人間と化してしまい、応用も効かなくなるでしょう。
集団で視野狭窄に陥ったまま、「正しさ」を飛び出した違う可能性、すなわち「間違い」を検討することもなくなるでしょう。異論は許されない状態、イエスマンだらけの組織になってしまえば、硬直化が進んだ結果、内外の変化にも対応できなくなってしまい、そのまま崩壊までまっしぐらです。
「何が正しいか」に囚われ、多様な意見に対する寛容さを失った結果、滅んでいった組織や国家というのも、いくつか思い浮かぶのではないでしょうか。
正しさを過信、盲信すれば、強い表現や発言はできるけど、その分大きなリスクも伴います。確かに「正しい」や「正しい側にいる自分」というのは心地よいかもしれませんが、それが必ずしも良いことなのかどうかは、再考の余地ありじゃないでしょうか。
「正しい」は支配や争いを生む
完全に蛇足な気もしますが、「正しい」が持つ負の側面について、ダメ押ししておきましょう。例えば、『論語』などのいわゆる四書五経を背景とする儒学や、その知識や「理」を重視する朱子学は、封建制度化の江戸時代や、科挙などの官僚制度における体制側にとって、都合のいいものとして重用されてきました。
明治維新以降も長らく、日本人の精神修養や秩序形成に多大な影響を及ぼしています。コミュニストや戦後の日本においては、マルクスやレーニンらの書物が「テキスト信仰」の中心に鎮座したように思います。
長幼の序や忠義、孝や礼儀といった「生まれ持った序列」を維持したい側、それによって格差を固定し、下剋上を抑制したい側にとっては、これ以上ないツールと言えるでしょう。
それではあまりにも観念論すぎて、現実と乖離してしまうとか、日本の在り方としては相応しくないという批判から、賀茂真淵や本居宣長らの国学や、知行合一や致良知といった、実践倫理を重視した陽明学派が力をつけ、明治維新にも大きな影響を与えたとも言われていますが、吉田松陰や西郷隆盛などの重要人物が打ち倒されてしまったため、結局は主流派になることなく、現代に至ったと私は考えています。
また、「自分たちの言動は正しい」と信じれば信じるほど、客観的な自己批判や周囲に対する思いやりや共感性が、徐々に麻痺していくような気もします。多数派や体制に反抗すると「非国民」だと槍玉に挙げられ、一度「敵」と認識すれば、一方的にどこまでも強く攻撃できてしまう。
自分たちの正しさを疑わず、組織やテキストに全てを委ねてしまえば、「正義vs正義」で争いは再現なくエスカレートしてしまうということも、私たちは歴史を通じて見てきたはずです。
「正しい」を盲信して同調したり、「正しさ」を振りかざして突き進むと、人間の支配欲や攻撃性が前面に出てしまう。それも、「正しい」の持つパワーと言えます。
「正しい」や「強さ」から、あえて離れる
冒頭でも述べたように、盲目的な「正しさ」や、そこから来る「強さ」に対して、本能に近い拒否感や苦手意識を抱く性分です。わざわざ意図して離れようと思わなくても、自然と距離を取ってしまいます。
「自分の正しさ」を疑わない人や、「正しさ」を肯定する集団や同調性にも、同じような反応を示すかと思います。(あからさまに顔や態度に出ないようにしているつもりですが、バレバレかもしれません)
「正しい」や「強さ」から離れ、距離を取るということは、必然的に「正しくない=間違い」や「弱さ」に身を寄せがち、ということになります。結果的に、既得権益や体制に楯突く側へ属しがち、味方しがちということでもあります。
なお、幼少期から現在に至るまで、なぜか「変わり者」を引き寄せがちです。大人しくて控えめで、口下手で自己主張も強くないのに、どこか周りとは違う独自のこだわりを持つ人。確かな実力を備えながら、目立つのが苦手だったり、周囲と足並みを揃えれば選ばれやすくなるとわかっていても、「それは嫌だ」と自分を曲げられない。経済的には中々勝てない「いぶし銀」な方々に、ついつい自己投影して肩入れしてしまうのも、変えられない性分なんでしょう。
長らく「正しい」とされてきたことに対して、誤解や誤りを指摘したり、新たな解釈から異論や革新をもたらすかもしれない、「正しくないこと」。伝統の裏打ちも、権威や多数派による支持もなく、弱くて取るに足りない存在かもしれません。ただ、それに目を向けて認めることこそ、本来の多様性や寛容さであり、組織や社会のレジリエンスを高めてくれるのではないでしょうか。
正しさ一辺倒や、高い同質性・強さ依存がもたらす脆さや危うさを中和するためにも、あえて「正しくないこと」や多様な「弱さ」を取り入れ、共存する。それは、行き過ぎた正しさを是正し、強すぎる発言を控えるためにも有効な手段だと考えています。
弱くて正しくない、「オリジナル」を支えたい
新しい商品やサービスなのに、早々に引く手数多で注目される「売れ線」や、独立開業したばかりなのに、瞬く間に有名人、有名企業としてのし上がっていく人たち。それはそれで「羨ましいな」と思う一方、「元々需要や理解される商品だから、革新性は低い」と、減らず口を叩くこともよくあります。
普通にやっても、中々勝ち目のない商品や、「売れ線」とは程遠いサービス。あるいは、どう頑張ってもリソースが限られ、そもそも勝負の舞台へ上がることすら難しい案件。予算や納期に余裕がなく、ビジネスオーナーご自身だけでなく、サポート側も厳しい条件になることも珍しくありません。
商売だけを考えれば、関わる理由がないどころか、大きなリスクにもなりかねない「弱い人たち」。それでも、難しいからこそ、共倒れのリスクも承知の上で支えたくなる。これも私自身が、反骨精神の強い天邪鬼だからでしょうか。
新しいことをやりたくて起業したり、今まで所属してた組織では出来なかった「自分ならではのこだわり」を表に出したくて独立したのに、これまでと同じ物差しで「正しさ」を判定され、長老たちに阿るような態度で「正しい」と評価されるのは、本当にやりたかったことなのでしょうか?
イノベーションや下剋上、世代交代を拒む人たちに擦り寄り、新しい可能性に蓋をする。あるいは、それを非難することで自分たちの立場を守る。その先に、「革新」も「将来世代」も、「私だけのオリジナル」もないでしょう。
独立した方が「もっと稼げる」とか、もっと正しい方に身を置いて、自分のステータスを高くすることが目的であれば、それに沿った立ち居振る舞いもあるかと思いますが、個人的にサポートしたくなるのは、「そうではない」方々です。
簡単には理解されないし、簡単に理解されてたまるかという自負もあるややこしさ。その性分ゆえに、社会や組織からはみ出たり、「正しい」とされる道を踏み外したり。「間違えるな」と押し付けられれば押し付けられるほど、あえて反抗したくなる人たちが隠し持つ、クリエイティブな「オリジナル」。
それがもたらすイノベーションを受け入れたり、世代交代にも対等に向き合ってくれる姿勢が一般的になれば、成熟した日本社会や市場も活性化して、健全な流動性がある、活気ある社会が訪れるのではないか、というのは個人の希望的な観測です。
何者かによる支配も従属も、立場の固定も拒む、予測不能の柔軟かつカオスな環境。「変わり者」や「弱さ」を許容し、むしろそれが強みになる時代を作るためにも、私はあえて「弱さ」や「間違い」に寄り添う味方で在り続けたいと思っています。
弱さ × 手段の正しさ
探検家である関野吉晴さんは、アフリカを出た人類が世界中に広がった要因、いわゆるグレートジャーニーの背景には、強さではなく「弱さ」にあると言います。確かに、群れを大きくすればするほど、すでに力を持っている者はその場に残り、何も持たない弱い者が、新天地を求めて生まれた場所を出ていくというのは、現代でも当てはまるような気がします。
ただし、弱さや弱者の立場を振りかざし、それを盾にするのもあまり良いやり方ではないでしょう。「弱さ」や多様な個性、「間違い」も活かしながら、強者である「正しさ」と伍していくには、手段や実践的な手続きにおける正解やセオリーといった、「正しさ」を踏まえる必要があります。
守破離を徹底して繰り返すことによって培われる、揺らぐことのない「正しさ」を真っ当に活用して、強者に一矢報いる。弱さを自覚するからこそ、手段に囚われない柔軟性や、変化を前向きに取り入れる姿勢を活かした、奇策や速さによる「一点突破」を主に据えるのも、「弱者の戦略」としてはセオリーと言えるでしょう。
私も一人の「変わり者」として、「正しさ」や多数派や権威を背景にした「強さ」には何度も辛酸を舐めました。特に、相手の立場やコンフォートゾーンが揺らぐからといって、ドリームキラーめいた「イノベーションのジレンマ」には、繰り返し苦労させられてきました。
相手が望む「正しさ」を押し付けられ、自分を曲げてそれに合わせる辛さも味わってきましたが、そういった相手に対して、「自分たちらしさ」や「弱さ」を変えないまま対峙するには、ちょっとしたコツや工夫と、磨き上げた技術が欠かせません。
徹底した「守」の段階を経ないと、自由な発想から来る「あえての間違い」を選択しても、上手く活用することもできないでしょう。
生来の感性や性分、これまで培ってきた経験やスキルを活かし、弱さや多様性、自由に寄り添う。私自身も類友だから、弱きを助け強きを挫く。最初からそこを目指していたわけではないものの、結果的に辿り着いたそれが、今後も大切にしたい私の在り方です。
私も変わり者かもと思ったら
この記事を読んで少しでも思い当たる節がある方は、いつでもお声かけください。アナタの同類が、マーケティングやWebサイト制作をサポートします。
また、もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
さて、月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら