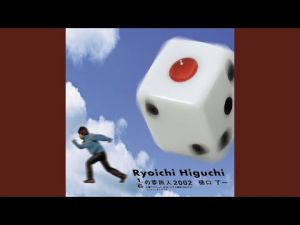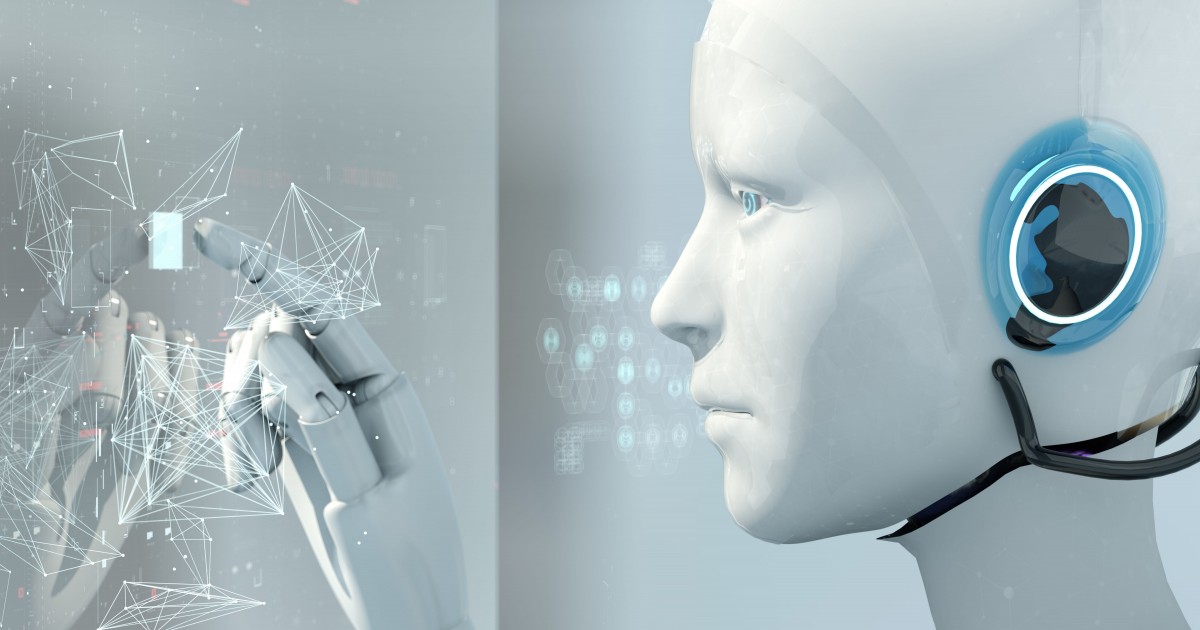月刊BLUEBNOSE 2025年07月号(#19)『世界中を僕らの ファンで埋め尽して』
何のためにSEOをするのか、コンテンツ発信をするのかということも絡めながら、あえてテキストオンリーのスタイルを選んでいる理由についても、長々と語っております。
ぜひ、最後までお付き合いください。
この記事が公開・配信される頃には7月も後半に差し掛かっていますが、実際の執筆時期は4月末頃。比較的手の空いている時期に、1本当たり5000字前後の記事を十数本、ギュッと固めて書き溜めています。
一本一本、少しでも誰かに喜んでいただけるよう、あの話もこの話もと思考を巡らせながら、できるだけ文字の多さを意識することなく、何の苦もなく最後まで読めてしまう「水のような文章」を目指しています。
文章においても、上善は水の如し。研ぎ澄まされてクリアな、雑味のないキレの良さ。そんな喉越しの良さを、日々追求しています。
しかし、そんなタイミングで休憩がてらSNSを覗いていると、「文章ばっかりの記事は読みにくい」とか、「箇条書きや表を使って、人にも検索エンジンにも受け取りやすくした方がいい」という投稿を見かけると、つい「おやおや?」と思ってしまいます。
水が良くないとできないことだし、余計な手を加えなくても、それだけで勝負できるという絶対的な自信がなければ、「それはそうですよね」と。過度の澱みや、視覚的、聴覚的なつっかかりを取り除き、流れるように最後まで読んでいただくには、それなりの修行と技も欠かせません。
磨き上げた水と技があるからと、(楽ができるので)「文章ばっかり」に胡座をかいていた部分もありますが、なぜこのスタイルを選んでいるのか、きちんとお伝えしたこともなかったかなと。
数多くのWebメディアやコンテンツが溢れている中、イマドキ、ここまでストイックに「ほぼテキストオンリー」で発信し続けているのも、珍しい方でしょう。なぜ態々、伸びにくそうな手段を選び、どんなメリットや思惑があって続けているのか。
今回はその辺りについて、改めてお伝えします。
箇条書きや表を駆使するのは、Excellent!
まず大前提として、箇条書きや表など、テキスト以外、より正確にいうならpタグ以外を用いて情報を整理し、検索エンジン的にもユーザーの視覚的にも受け取りやすくするというのは、大変素晴らしい取り組みだと思います。
情報、ある種の「答え」を探しに来た人にとっては、「それ」が一目で分かるように箱詰めされ、お土産のように持って帰りやすくなっていると、非常に嬉しいですよね。重要なキーワードや要点、大事な数値が文字に埋もれてしまい、どこにあるか分からない。そんな状況で、冒頭から全部追いかけないというのは、誰もが辟易します。
前者が持ち込みOKなテストにおけるアンチョコやカンニングペーパーだとすると、後者は現代国語や英語の長文読解の問題文みたいなものでしょう。問題と関連する傍線付近だけを摘んで、簡単に解けるときと解けない時があり、時間が限られている場合には「面倒くさいな」と思うことも、多々あります。
「パッと一目でOK」という視認性や分かりやすい資料という点では、一枚モノのチラシやポスターといった広告、店頭や街角のフリーペーパーや小冊子、屋外の案内板や掲示板なども同様ですね。
どんなに急いでいる時でも、それ一つで情報を網羅できますし、繰り返し見る時にも便利です。
数学や理科の教科書での公式が載っている部分だったり、参考書の単元ごとの要点整理、最近だと動画投稿サイトの「まとめてみた」や「ゆっくり解説」といったコンテンツも、これに近いかもしれません。
情報を受け取る側としては一瞬の出来事ですが、作る側、整理する側にとっては、結構な手間がかかっています。Web上であれば、CSSでのスタイリングも気にする必要がありますし、何も考えずにtableタグを使ってしまうと、小さい画面では極端に読みにくくなるため、特殊なレスポンシブ対応を考慮しなければなりません。
紙媒体やスライド、動画の場合なら、Webサイト上以上に、視覚的なデザイン性を求められることもあり、足りない要素は自分で一から作り出さなければなりません。こういった事前準備や、仕上がりのチェックにかかる労力やコストは相当なものですし、時代が進むにつれて「分かりやすい」の基準自体が変遷してしまうため、常に追従し続ける覚悟も必要です。
一人のWebクリエイターとして、その大変さは身に沁みて理解しています。テキストのみのコンテンツと比較して、遥かに手間がかかる上に、維持やメンテナンスも大変な「(視覚的な)受け取りやすさ」を追求する姿勢には、素直に頭が下がる思いです。
情報のチェリーピッキングも起こりやすい
箇条書きや表も取り入れて、「これさえ見ればOK」と情報を受け取りやすくすると、ショートケーキのイチゴだけ持っていかれるように、「一番美味しい部分だけ」を摘まれてしまうかもしれません。
例えば先ほど例に挙げたカンニングペーパーや、教科書の公式が掲載されているページ。持ち込みOKのテストで使ったり、テスト期間の暗記や一夜漬けにだけ貢献してくれればいい。試験が終わったら用済みで、パッと忘れてしまう。そんな経験、ありませんか?
蛍光ペンでマークしたところしか読まず、前後の文脈は頭に入っていないので、対象範囲の広い実力テストや、実際に必要な場面で「全然理解していない」という現象も起こりがちです。
チラシや小冊子も「情報が欲しいから」と、それだけを持ち帰ることはよくあります。結局は、パッと眺めて満足してしまい、実際にチラシに掲載されているお店へ足を運んだり、小冊子で紹介されている商品を買ってユーザーになるケースは、どれほど多いでしょう。恐らく、大半が「比較検討」に使うだけで、そこから次のステップへ移る人はごく少数です。
確かに、SEOとしては効果が高いでしょう。検索したキーワードに対して、「答え」がしっかり返ってくるから。アクセスされやすくなれば上位獲得にも繋がりますし、アクセス数やPVも自然に伸びていきます。
また、すでにアクセスが多い既存ページを、中身を大きく変えずに、情報を受け取りやすく改修するのも効果的でしょう。交通量の多い交差点や、よく見られている看板を、要所を押さえたまま見やすいものに掛け替えるようなものだから。
でも、だからといって、そのコンテンツが掲載されているWebサイトやドメイン、ブランドや企業に対して、少しでも印象が良くなっているか。そのSEOが事業に貢献しているかと言われれば、必ずしもイエスとは言い切れません。
調べればすぐに欲しい情報が手に入る。だからその場限りで便利に使われ、困り事が解決すれば、すぐに忘れられてしまう。瞬間的に情報を「使い捨て」られるだけ。そして下手をすると、それに応えるためだけに、こちらが振り回されるようにもなりかねない。
そうなっても仕方ないですよね。だって、バナナの皮を剥いて一口サイズにカットし、爪楊枝まで刺して「試食できます」と並べてあれば、「試食だけするな」という方が無理でしょう。
もちろん、試してもらわないと良さが伝わらないとか、「先義後利」の精神も大切です。でも、オンライン上では、目の前に相手が見えている訳ではありません。本屋での立ち読みに比べれば、Web上に陳列されている情報を持って帰って、都合よく使い捨てるだけといった不義理の方が、遥かにハードルが低いはず。
その不義理な行動を誘発しているのは、試食を用意した側にもある。その事実は、きちんと理解しておくべきだと思います。
カットフルーツな中身より、等倍速の映画やそれ以下の読書
贈答用の高級な果物や、立派な鮮魚をいただいたとしても、「これ、どうやって食べるん?」みたいに困った経験はありませんか?お魚であれば、捌いたり下ろしたりするのが得意な方も沢山いそうですが、普段使いするのなら、調理済みの切り身や柵の方が便利です。果物も、皮を剥いて、食べやすいサイズにカットしてあるカットフルーツの方が、気軽に食べられます。
でも、カットフルーツにしてしまうと、結局は「試食のバナナ」と同じです。つまみ食いしやすい分、「モノ」としての消費度合いが高く、「コト」、体験としての思い出は残りにくいのでは。面倒くさくて値段は張るし、カットフルーツと味は同じであっても、わざわざ農園へ足を運んで「イチゴ狩り」をしたり、砂浜や川辺で「スイカ割り」をした方が記憶に残るアクティビティです。
また昔から速読が流行っていて、最近では映像作品の「倍速再生」や「ファストムービー」も珍しくないそうですが、速読に関しては、時間をかけてゆっくり読んだ場合と比較して、理解度が低い傾向があり、繰り返して何度も読まないと効果が薄いという意味では、早く読めてもあまり意味はなさそうだという結果も出ています。
映画の倍速再生も「内容は追えるけど、なぜそうなったのか分からない」といった理解度の低下や、感情移入がしづらくなるといった弊害が指摘されています。教科書の重要なところだけに線を引いて覚えようとする学習方法と、似たような現象が起こっています。
重要な部分だけを抜き取って、そこだけをピックアップしたところで身につかない。食事と比較して、サプリメントの吸収効率が低いのも、何となく似ているような気がしますね。
つまり、ここで重要となるのは情報の中身やコンテンツの主要な部分、美味しい部分だけを提供するのではなく、その前後にある部分、情報全体を丸ごと味わってもらうことにある、とも言えないでしょうか。もっと言えば、コンテンツの中身や伝えたいことなんてどうでもよく、雰囲気や行間こそに力を入れて、そちらを楽しんでもらう。
「何が言いたいのか」をできるだけ早く提供し、サッと持って帰ってもらうのではなく、それを明確に切り取らず、じっくり時間をかけることでコンテンツ全体やブランドに対して、深い理解を期待する。それには、横書きで左開きになる教科書や参考書的なスタイルではなく、縦書きで右開きになる「難しい本」スタイルの方が向いているのではないか、という考え方です。
本当は、縦書きの方が文字を追いかけるスピードも遅くなり、深く考えながら読んでいただけるんですが、Web上だとどうしても、writing-modeによる縦書きと、その挙動がブラウザごとにバラつくため、E-PUBを使った電子書籍のような形でないと向いていません。そのため、その点は妥協して「横書き」という判断をしています。
肝心の中身より、行間や雰囲気、空気感を大事にしているように思える番組例としては、北海道テレビ(HTB)制作のバラエティ深夜番組『水曜どうでしょう』や
毎週日曜日の朝7時からフジテレビ系列で放送されているトーク番組、『ボクらの時代』あたりでしょうか。
NHK総合で放送されているドキュメンタリー番組、『ドキュメント72時間』も、若干近い印象です。
『水曜どうでしょう』といえば、「サイコロの旅」などの「特殊な旅番組」でロケを中心とするドキュメンタリーの要素が強く、旅番組であるにも関わらず、「旅先で何をやるか」にはあまり重点を置かれていません。何なら、せっかくの海外旅行なのに、目玉となりそうな施設はことごとく休園日だったり、有名なグルメをあえて食べないといった展開も、多く見られます。
結局、2名の出演者と2名のディレクター陣の関係性や、数々のハプニングに対する出演者のリアクションなど、過程や空気感が面白いため、「中身はどうだって良い」という番組です。
『ボクらの時代』は、ゲスト同士の自由なトークを主体とした番組ですが、視聴者が惹かれるのは話題そのものよりも、ゲスト同士の組み合わせの妙味や、お互いにどんな風に振る舞うかといった「空気感」です。具体的に何を話したかは、二の次、三の次という印象です。
『ドキュメント72時間』の「とりあえず72時間撮影しっぱなし」がベースになって、そこから1本の番組に仕立てるスタイル。特別な出来事やドラマチックな演出に頼らず、何気ない日常の断片や、「何でもないところ」から面白さを拾い上げる作り方になっています。
それの何が面白いのか、本当に人気になるのかと思われそうですが、『水曜どうでしょう』は北海道テレビ発の低予算番組でありながら、全国47都道府県全てでの放送を達成しています。レギュラー放送終了後も、四半世紀以上にわたり同局の重要なコンテンツであり、現在も数年に1回のペースで新作が放送されています。
DVDも度々販売リリースされ、イベントには「藩士」と呼ばれる熱心なファンが全国から集まるなど、その人気は衰えるどころか、成長し続けています。
これらの番組が採用している「行間」や「雰囲気」重視のスタイルを、そのまま踏襲しても上手く行くとは限りません。例に挙げた番組が特殊なだけかもしれませんが、上手くやりさえすれば、伸びていく可能性は十分にある。それが、「テキストオンリー」をあえて採用する背景です。
理解の遅さとリピートがポイント
情報やコンテンツとして、「書いてあること」や「中身」で勝負してしまうと、どうしても「分かりやすさ」や「手軽さ」に重点を置いてしまいますが、それだと「一回限り」で終わりがちです。その後リピートが起こったとしても、主要な部分、サマリーとしてまとめてある部分しか触れないでしょう。
ミステリー小説を『このミステリーがすごい!』に選出されたものから選ぶ方もいらっしゃると思いますが、『このミステリーがすごい!』に選ばれた名作でも、作中のトリックや叙述、伏線やストーリーラインの構造が「すごい」のであれば、最初の一回で満足してしまいます。「あれ、あそこはどうだったっけ」と最後まで読み終えてから、該当部分を読み返すこともなくはないですが、何度も何度も読んで楽しむ人は少数派じゃないでしょうか。
その一方で「難しい本」スタイルや、空気感や行間を大切にする伝え方だと、最初の一回では「よく分からない」と思われるかもしれません。途中で「理解が追いつかない」と中断し、理解を諦めることもあり得るでしょう。でも、後々になって何度も何度も繰り返し紐解いてしまうのは、「理解が難しかった本」や映像作品じゃないでしょうか。
「書いてあること」をそのまま受け取るだけでは理解できないから、前のめりになって「書いていないこと」にまで想像力を働かせようとする。そうすると、その都度、読み手が勝手に「新たな解釈」を紡ぎ出す。「これは、こういう受け取り方もできたんだなぁ」と。大人から子供まで夢中になるコンテンツ、大人になってから再読しても、得られるものがある名作には、そういう奥深さも自然と備わっています。
折に触れて、「人生に大切なこと」を教えてくれる、「自由な解釈」を許してくれるコンテンツは、単なる「情報」から、人生を共に歩む「座右の書」へと変化します。定期的に帰って浸りたくなる「世界観」があるからこそ、ファンになってしまう。
比較検討中で需要はあるけど移り気なユーザーに対して、広告やPRの観点で「使える情報」を定期的に発信するようなSEOと、いつかファンになってくれるかもしれない未知のユーザーに対して、自分たちの世界観を理解してもらうようなパビリオンやアトラクションを、一つ一つ作っていくようなSEOと。
どちらが上か下かという話では全くなく、そういう選択肢も存在しますよ、というお話です。
UXは不可視かつ制御不可
箇条書きや表もなく、テキストオンリーはBad UIでUX的にも悪い。これも誤解があるような印象です。
まず、テキストオンリー自体がBad UIかというと、必ずしもそうではないのでは、というのが今回の本筋です。UXの観点からみても、使い方次第で十分に生かすことは可能です。
もちろん、長文がダラダラと続いたり、改行が少なく、漢字の割合が高くて黒い塊のような文章になってしまうと、流石に私でも「読みにくいな」と思うので、それは避けるべきです。適当に改行や空行を挟めば、テキストだけでも十分に読みやすさは確保できると考えています。
ただし、一行あたりが40文字を超えても折り返さないレイアウトや、見出しでもない場所で中央揃えを用いる文章は読みにくいので、「黒い塊」と合わせてBad UIでしょう。
またUXについてですが、広義のUIを指していることが多く、本来の意味とは少しズレています。テキストばかりの場所へ箇条書きや表を挿入すると、確かに「情報の受け取りやすさ」は向上します。しかし、それがすなわちUXの向上かというと、そうではない、というのが私のスタンスです。
UXとは本来、対象物とユーザーとの間に生まれるものであり、直接視認できるものではありません。また、ユーザー側の受け取り方次第で決まるため、提供側は「こう感じてもらえたらいいな」と願いながら工夫することや、アフォーダンスを駆使したデザインを通じて、受け取りやすさのチューニングは可能ですが、「こう感じなさい」と指図することはできません。
UXとは、「内心の自由」に属するものです。何をもってUXが良いか悪いかを決められるのは、本人だけと言えるでしょう。
また、提供側が想定する「本当の顧客」にとって、ベストなUXというのも様々です。例えば、一般的には店内が清潔で新しい飲食店の方が好まれると思います。その一方で、小汚い裏路地の民家みたいな町中華や、個人経営の居酒屋を好む人もいます。
そうした「昭和レトロ」を味わいたい層にとって、壁にかかったメニュー札を「読みにくいから」と真新しいものに変えることが、良いUXに繋がるでしょうか。
また、往年のキャンペーンガールのポスターや、すっかり古びたカレンダーを一新し、壁や床の汚れを完全に除去することが正解でしょうか。座りにくいビールケースの椅子も、取り替えるのがベストでしょうか?
結局、そのお店らしさを求める人たちにとって、ベストなUIやUXというものは異なります。表面的な物差しだけでベストなUXを想定するのは適切ではない、ということです。
つまり、そのSEOやコンテンツを通じて、どの顧客に働きかけたいのか、どんなUXを感じ取って欲しいか。それらとコンテンツのUIや狙いが噛み合っているかどうかが重要なのであって、「情報の受け取りやすさ」だけが必ずしも正義とは言えない、という話でもあります。
広告やPRだけでは、弱者にも世間的にもBad
商材や企業、ブランドの良い情報や受け取って欲しい情報だけを切り取って、綺麗に再加工し、「受け取りやすさ」を強調するのは、一瞬の広告やPRとしては有効でしょう。露骨にデメリットを強調している広告は、あまり見かけたことがありません。
ただし、元々の強みや差別化ポイントが、強者ほど豊富ではない弱者にとってはどうでしょう。せっかく持っている他社との違いも、良い部分だけを抽出してさらに切り刻んでしまうことで、100%あったはずの差異が目減りしてしまいます。
それを避けるために、私たちBLUE B NOSE(以下:BBN)では、一般的には「悪い」される部分やデメリットも、愛嬌と受け取ってくれる相手、丸ごと全部愛してくれる人へ向けてPRすべきだとお伝えしてきました。「切り取って整形する」のは、あまり良い方法だとは思えません。
ましてや、広告やPRの観点だけでSEOやマーケティングを考えているのであれば、顕在化している需要層に対するゼロサムゲームというか、レッドオーシャンで奪い合いをしているようにも思えて来ます。
確かに、すでに動き始めている層へ向けて、競合の中で目立つ場所を確保できれば、まだ見ぬ顧客へアプローチするよりも、時間もコストも抑えやすく、アクセス増加やコンバージョンには繋がりやすいかもしれません。
しかしながら、その人たちはあくまでも「広告やPRに吸い寄せられてきた」だけの人たちです。その商材や企業、ブランドの理念やこだわりまで理解してくれているとは限りません。
一回限りの接触で終わってしまう可能性も高く、むしろ、少ない固定客に対してLTV向上を図った方がいい弱者にとっては、あまり好ましい考え方とは言えないでしょう。
また、「分かりやすい情報」の表面的なところだけしか受け取らず、極端な解釈をして「お客様は神様だ」とカスハラ気味になってしまう、ペルソナ・ノングラータである可能性も秘めています。多少なりとも売上を上げたのに、言葉を駆使しても理解してもらえないために、かえってマイナス要因になる厄介な人たちを避けるためにも、安易に「情報を受け取りやすく」しない方がいいとも考えています。
最終的に、「やっぱり『顧客』じゃなかった」場合でも、あえて受け取りにくくしている情報を読み込んで、理解した上で近付いてきてくれている相手であれば、「日本語は読める」確率が高いので、言葉を尽くせば、そんなに悪い結末にはなりませんしね。
いわゆる従来型のSEOとして、「情報を受け取りやすく」する路線や、広告やPRであることを重視したやり方も取りながら、並行してドラッカーが『マネジメント』の中で述べていた「顧客の創造」という基本にも立ち返ること。今はまだ需要がはっきりとあるかどうかも定かでない、未知の層へ向けて「本来の顧客」であるファンになってもらうよう、世界観を構築し、パビリオン的に一つ一つ切り出していくようなやり方も、弱者にとっては避けられない「基本」であるように思います。
ゼロサムに加わるだけでなく、顧客のパイ、需要のパイを増やすSEOやマーケティング。それをサポートして、面倒な方向へ進ませるのが我々が担う「世間よし」じゃないでしょうか。
ドラッカーを踏襲し、「世間よし」を実現するためには、分かりにくい違いを丁寧に伝え、ゆっくり時間をかけて理解してくれる人へ向けて届けるしかないでしょう。本当にそれで上手く行くのかどうかの実践や実証も含めて、あえてテキストオンリーで人を選ぶコンテンツ発信を選択しています。
受け取りやすくする方が、ベストではある
テキストだけではなく、適切に箇条書きや表を挿入し、情報を受け取りやすくすること自体は、非常に素晴らしいことというか、できるならやった方がベストです。私がテキストだけにしているのも、そちらの方が準備が少なくて済むし、楽ができるという理由も少なからずあります。長々と述べてきましたが、半分以上は自分にとって都合のいい、ただの屁理屈かもしれません。
できることなら、テキストの多いコンテンツも見やすくなるように、推敲を加えたいなとも思いますが、それと同時に「分かりにくさ」の利点もあるのは間違いないので、周りが「受け取りやすさ」に力を入れるのなら、差別化も兼ねてあえて背を向けてやろうという魂胆もあります。
分かりやすくすることのメリットもあれば、デメリットもある。
即効性がある反面、レッドオーシャンや価格競争にも巻き込まれやすい前者か、時間はかかるけれども、軌道に乗れば不利な競争を避けて、無理をしなくても済む後者か。どちらがステークホルダーにとって向いているのかを、総合的にご判断いただけたらと思います。
もし、心身ともに無理をせず、持続させやすい成長を望むのであれば、長期的に役立つ資産を作るつもりで、またその資産を通じてファンを獲得し育てていくつもりで、まだ「本当の顧客」に向けた読みにくいコンテンツや、分かりにくいコンテンツを用意することをオススメします。
人口減少は避けられないご時世で、限られた人数を相手にLTVを上げられる方法や、長く深く続く関係性を構築できる方が向いているはず。良いところだけでなく、悪いところも丸ごと受け止めてくれる相手と出会えるように、情報発信し続けましょう。
世界中を僕らの ファンで埋め尽そう
ただの個人的な発信スタイルについて解説するだけのはずが、色んなポリシーやBBNとしての在り方や目的までギュギュッと出てきてしまいましたね。本当のところは、ただ楽をしているに過ぎないんですが、その背景に色んな思想の積み重ねもあるんだなと、少しでも伝わるようであれば幸いです。
一度受け取ったら終わりではなく、何度でも触れたくなるし、何度触れても新しい発見や解釈がある。そういう名コンテンツを目指して、一本一本しっかり作っています。
目先のUIではなく、コンテンツに触れたことで醸成される総合的なUXを重視して、小手先の見せ方を工夫するのではなく、世界観を支えるアトラクションやパビリオンのつもりで向き合った方がいい。
そういう発想で、アナタの世界観構築を支援し、長く続けやすい無理のないカスタマーサクセスをお手伝いするBBNと、Webサイト制作や、コンテンツを用いたWebマーケティングに取り組んでみませんか?
ゼロサムの奪い合いに参加して、無理に頑張り続けるのはもう十分だ、自分たちにあった楽な取り組みをしたい、楽になる情報発信をしたいという方は、ぜひ気軽にお声かけください。
"How do you like SEO?"
また、もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら