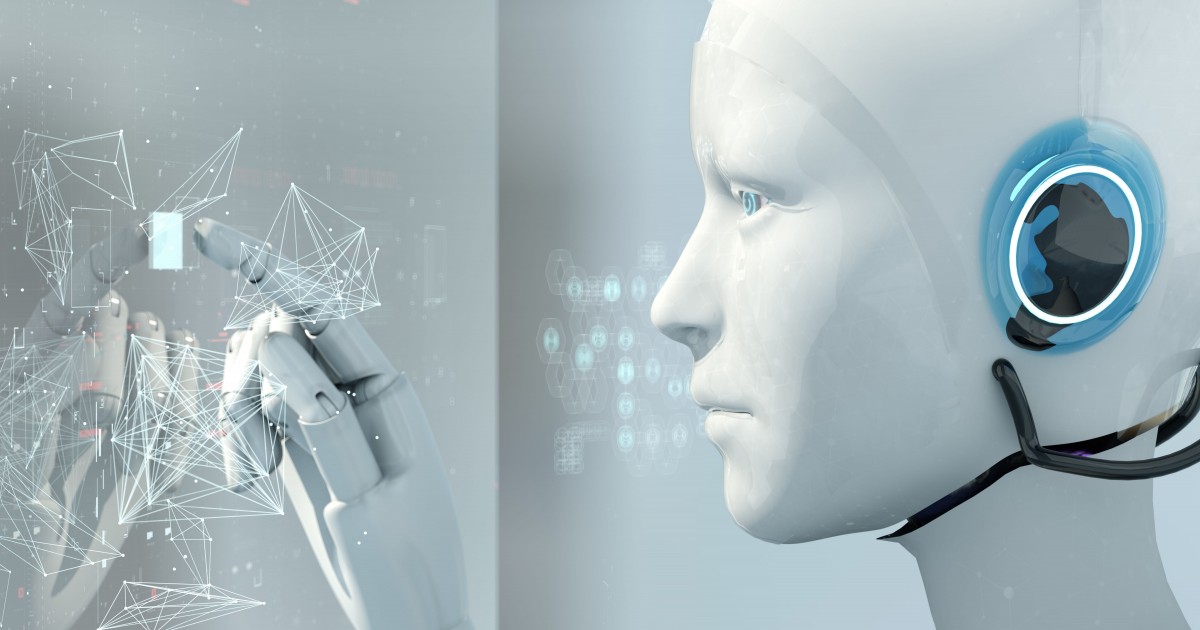月刊BLUEBNOSE 2025年04月号(#16)『COVIDawn-25 朝まだき』
内輪でしか通じない耳慣れない造語を、安易に使ってはいけない。周囲には口酸っぱく言っている立場ですが、今回は、タイトルから"COVIDawn"。COVID-19と、夜明けを意味する"dawn”を掛け合わせたこの造語には、新型コロナウイルスの5類引き下げによって訪れた、ある種の「コロナ禍明け」の空気感を込めています。2023年5月の5類移行から、まもなく2年となることから、"COVIDawn-25”としてみましたが、いかがでしょうか。
コロナ禍の夜明けを意図した造語なのに、タイトルは『COVIDawn-25 朝まだき』。まだ夜が明けきらない「朝まだき」を組み合わせています。新型コロナが5類へ移行し、感染者数も報じられなくなれば、ウイルスは徐々に影をひそめ、経済も社会も元の姿を取り戻す。そんな期待もあったことは確かです。
しかしながら、2年が経った今、素直に「夜明け」とは言い難く、感染や医療機関の逼迫も、一定の周期で増減を繰り返しています。
結局のところ、5類移行前と何も変わっておらず、もし「変化」があったとすれば不正受給の発覚や、総理大臣の交代とそれに伴う日本経済の失速、さらには、米国でドナルド・トランプが大統領へ返り咲いたことぐらいでしょうか。
積極財政派の経済通だった安倍晋三元総理は暗殺され、安倍派と呼ばれていた「清和会」の面々は冷遇されてしまい、政敵であった岸田文雄前総理によって、永らく冷飯ぐらいだった石破茂氏が総理大臣に就任しました。石破内閣が発足して以降、財政再建が過度に重視されるようになり、経済の冷え込みが加速しています。
ロシアのウクライナ侵攻や、スエズ運河、紅海、パナマ運河など、主要なシーレーン周辺での政情不安に端を発したコストプッシュインフレは、いまだ収束の兆しを見せていません。
また、激化する米中経済対立は人件費が高騰しつつある中国からのキャピタルフライトを加速させ、物価や燃料費の高騰を抑えるために、消費減税や社会保険料引き下げ、最低賃金に合わせた基礎控除引き上げ、暫定税率の廃止といった政策が望まれましたが、結果はご存知の通りです。
減税策は全て潰されてしまい、現政権は民間企業に対して「賃上げ」を連呼するばかりです。さらに、この春からはトランプ大統領が就任前から掲げていた「関税の引き上げ」が執行されつつあります。日本に対しては消費税引き下げの要求が示され、輸出が厳しくなるならば、国内需要を喚起し、消費を促進するためにも減税策は一石二鳥、三鳥のはず。依然として機敏な動きや具体的な決断は見えてきません。
札束に火をつけて灯りを照らしてくれる成金や、立派な長者でもいてくれれば良かったんですが、明るい材料はあまり多くない状況です。そのため、タイトルには「朝まだき」を合わせています。
今回は、手元にある情報やヒントをもとに、現状をざっと考察し、いくつかの見通しを整理してみます。なお、経済の専門家ではないため、素人の見解も多々あるかと思いますが、その点はあらかじめご了承ください。
家計は逼迫気味?
まず見ておきたいのは、『2024年度「飲み屋」さんの倒産 最多の276件 値上げが難しく、食材・光熱費の高騰などが直撃』という記事です。
次に、『2月の実質賃金2カ月連続マイナス 「現金給与総額」前年同月比3.1%増も…厚労省「物価高に追いついていない」』や
『賃上げ、社会保険料に消える 負担率2割で高止まり』といった記事があります。
さらに『令和7年度の国民負担率を公表します』では
年々増えていく再エネ賦課金は含まれていませんが、再エネ賦課金自体は『再エネ賦課金が過去最高 32年ごろまで増加 専門家「国民の許容範囲超えている」』とも報じられています。
一年で実質二倍となっている米の価格高騰や、原発再稼働を抑制し、火力発電に依存し続ける状況も続けば、光熱費も簡単には下がらないでしょう。
財務省の発表では「令和7年度の国民負担率は、46.2%となる見通し」ですが、賃上げをしても社会保険料に吸収され、実質賃金も物価に追いつかず、先の見通しとして減税が見込めないとなれば、真面目に働く現役世代や子育て世帯は、簡単に「余計なもの」へ手を伸ばさないでしょう。
広告やマーケティングをクライアントへ提案し、エンドユーザーへ仕掛ける業界人としては、この状況は非常に好ましくない状況です。生活必需品に対して消費者は、いつもと同じものをリピートするか、質を下げて少しでも安いものを買おうとするでしょう。そこへ、「これは要りませんか?」と宣伝を仕掛けたところで、むしろ嫌な顔をされるだけでしょう。
例えば、卵や牛乳を目玉商品として「1,000円以上のお買い上げで198円、おひとり様一個まで」といったプロモーションをしてしまうと、安売り商品だけを目当てに買い物をされてしまいます。その結果、売り上げは上がっても利益は微々たるものに終わってしまい、最終的にはクライアントを苦しめることになるかもしれません。
薄利でもいいから売り上げを上げ、利益を出して回転させることが大事だというお気持ちは理解できますが、そればかりを追いかけると、やがて企業の個性は失われ、価格競争から抜け出せず、精神的にも疲弊してしまうでしょう。
飲み屋さんのように、「非必需品」の中でも比較的お手頃価格で普段の生活に隣接している業態であっても倒産が最多という状況です。それ以上に高価で宣伝もしづらい業態や、普段の生活から離れた「ハレ」の商材に対しては、クライアントにもエンドユーザーにもアプローチが一層難しくなっています。コストが嵩む割には、結果が出ず、利益にも結びつかないとなれば、広告やマーケティングの出番はありません。手間暇をかけてコンセプトや理念、他社との違いを説明されても、それに付き合う時間も予算の余裕もないというのが本音でしょう。
あくまで筆者の肌感覚ですが、2020年4月の第一回目の緊急事態宣言やその後のコロナ禍と同じくらい、あるいはそれ以上に厳しい状況だと感じています。宣伝広告やプロモーション、広報を通じて「必需品」以外に人々を動かすことが難しく、クライアントにコストを割いてもらうのも難しい状況じゃないでしょうか。
家計の余裕、つまり可処分所得を増やすために、何らかの減税措置が取られれば話は変わってきますが、現時点ではその兆しが見られません。政治に過度な期待はせず、自ら手を打つ必要があるでしょう。
メディア、広告そのものが揺らいでいる
まずは、事実を確認しましょう。『2024年 日本の広告費』
『データで読み解く、コロナ禍前後の生活者行動とOOHメディアの可能性』
これら2つの記事によれば、日本の広告市場は3年連続で過去最高を更新。インターネット広告費は、総広告費の47.6%を占めるまでに成長しています。一見すると、業界は好調に見えますが、単純に楽観視できる状況かというと、そうではありません。
大前提として、コロナ禍以前、つまり2019年までとそれ以降とでは、生活動態や働き方が大きく変化しており、その影響は現在も色濃く残っています。
例えば、リモートワークの導入によりオフィスを縮小したまま、リモートとオフィスへの出社を併用している企業もありますし、そもそもオフィスそのものを地方へ移したり、生活拠点を郊外や地元に移した方も少なくありません。
こうした状況を見る限り、完全に以前の動きへ戻るとは考えにくく、「分散化」や「多様化」といった傾向は今後も続くでしょう。かつてのように、大勢が自然と都心に集まり、決まった時間に一斉に帰宅ラッシュを迎えるといった想定が、今後も通用するかどうか、答えは言わずもがなでしょう。
参照記事によると、交通広告のうち「特に鉄道は、車内ビジョン、中づり、ステッカーなどの車両内の媒体が前年を上回った」とのこと。
しかしながら、筆者がよく利用するJR西日本の京都線では、コロナ禍以降、JR西日本関連の自社広告やマナー広告が大半を占め、その他の広告はごくわずかという印象が続いています。網棚の上は現在もスカスカです。
沿線の私立大学や予備校、学習塾、美容系、脱毛サロン系などの広告は以前から根強くありましたが、最近では大手の脱毛サロンが破綻したこともあり、紙媒体の掲載量はさらに減少したように感じます。
また、学習塾関連でも急な経営破綻が報じられるなど、不安定さは否めません。そうした背景を考えると、車内向けの紙媒体がかつての水準に戻るには、もうしばらく時間がかかりそうです。
インターネット広告でも動画広告が伸びているということなので、車内ビジョン向けの動画広告が増えているのかもしれません。しかしこれは筆者の憶測であり、偏見の域を出ない偏見です。
その一方で、新聞の折込や購読者数の減少を補うように、かつては折込で配布されていたようなチラシが、ポスティングとして配られるケースが増えている印象です。新聞の発行部数、そして紙媒体の雑誌や出版物は、良くて横ばい、基本的には減少傾向が続くでしょう。出版物が持つ影響力も、少しずつ着実に減退しているように思えます。
出版物の影響力が着実に減少している中で、それ以上に信頼や存在感が大きく揺らいでいるのは、地上波の民放各局やNHKでしょう。
タレントの問題に端を発し、今もなお騒動の渦中にある印象が強いフジテレビを筆頭に、千葉県知事選の投開票前日、候補者の一人である「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志氏に対して、公平性を欠いた報道を行ったと指摘されたTBS。『セクシー田中さん』をめぐる対応や、『24時間テレビ』の寄付金着服事件のあと、何事もなかったかのように同番組を継続した日本テレビ。
NHKは、『クローズアップ現代』に対するやらせ疑惑や、事実と異なる映像を使用した「緑なき島」の件で会長が元島民に謝罪するものの、自社のニュースで取り上げることさえ行いませんでした。
極めつけは、兵庫県知事選の結果に象徴されるように、各局が県民の民意を正しく読み取れず、その流れを覆すことすらできなかったという現実です。大手新聞やテレビの影響力がすでに限界を迎えていることを示しており、不信感はさらに広がっています。SNSの規制にまで話題が発展したことからも、既存メディアの影響力低下は著しいと言えるでしょう。
その一方で、任天堂が自社コンテンツを通じて情報発信を行ったり、トヨタが「トヨタイムス」を自社で運用しているように、影響力のある企業は「既存メディアに頼らない」情報発信の形を確立しています。せっかくスポンサーとして広告を出していても、テレビ局や出演者の不祥事によってACジャパンのCMに差し替えられてしまっては、広告費の意味も薄れてしまいますからね......。
広告市場全体としては成長を続けているものの、その屋台骨となるはずのメディアそのものが揺らいでいます。特に、地上波テレビや大手新聞、NHKについては既に「広告を打つだけの価値があるか」が問われており、大手企業も認知を維持するために売り上げに貢献しないと分かった上で、出稿しているケースが多いようです。
もっとも、NHKをはじめ多くのメディアが、今や「不動産業」が主な収益源になっている構造を見れば、広報や報道といったメディア部門は、もはや副業程度なのかもしれませんね。
デジタルも、アドネットワーク、アドフラウドと問題山積
以前、『モバイルファーストなら、広告にも気をつけたい』で、スマホやタブレットといったタッチ操作が中心のデバイスと、現在のWeb広告の相性の悪さについて触れました。
意図しないタップや誤クリックを誘発する設計、そして広告そのものへの不信感など、ユーザー体験と広告の関係は、決して良好とは言えません。
さらに最近では、著名人を勝手に使ったSNS上での詐欺広告や、大手Webメディアにまで表示されている「アドフラウド(広告詐欺)」も問題視されています。
『料理レシピ紹介サイトなどに性的広告 運営会社が対策強化へ』と、子供も閲覧する可能性のあるサイトに「エロ広告」が表示されていたとして、国会でも取り上げられる事態にまで発展しており、アドネットワークの透明性や事業者の管理体制が問われています。
鉄道の時にも触れましたが、デジタル広告で伸びているのは恐らくWeb用の動画広告や、動画サイト関連でしょう。あるいは、電子書籍内での広告出稿や、スマホアプリ内でのインフィード広告やリワード広告といったフォーマットも、地味に成長しているのかもしれません。
さらにSNSを通じたショート動画や縦動画関連も、恐らく伸びていると思います。ただし、筆者の無責任な推測の域を出ません。
一方で、リスティング広告やディスプレイ広告は、すでに出稿するのが馬鹿らしくなるほど荒れている印象です。検索結果画面が広告だらけで、広告とコンテンツの主従が逆転している印象です。本来の検索需要を満たしにくくなっている上に、辿り着いた先が中身の薄いコンテンツや、AI生成と思しき低品質なページだったりすると、ユーザーとしても辟易してしまいます。
SEOの「負の最適化」が進んだ結果や、生成AIの登場によって、検索需要自体が減少し、Googleへのトラフィックすら、減少傾向にあるとも言われています。
そんな中、唯一の“希望の星”だったSNS広告に関しても、各プラットフォームの栄枯盛衰や仕様変更の激しさについていけず、運用以前の段階でつまずいてしまうケースも少なくありません。
つまり、「デジタル広告が伸びているから安心」や「とりあえずWebやSNSへ出稿しておけば大丈夫」といった楽観的な判断は、もはや通用しない時代に入っていると言えそうです。
夜明け後なのに、夜明け前より暗い
COVIDawn。それもCOVIDawn-25。2年が経過した今でも状況は明るくなるどころか、2020年の緊急事態宣言下より悪化しているのではという懸念すらあります。
現在の石破政権が、トランプが仕掛けた関税への対応にも苦慮し、米中の板挟みのなかでバランス外交を模索するあまり、親中派や親韓派の勢力に呑み込まれてしまう可能性もあります。親北寄りと見られる大統領が誕生するかもしれないという報道もあり、外交面での悪いニュースは着実に積み上がってる印象です。
思い返せば、コロナ禍にはまだ安倍元総理が健在で、休業支援、雇用調整助成金、各種給付金や借り換え支援といった比較的分かりやすく、実効性のある支援策が充実していた印象があります。
今も、血眼になって探せば補助金や助成金制度が見つかると思いますが、あの頃の手厚いセーフティネットがあるとは思えません。
減税を求めてもまともに取り合わず、財政健全化という誰も求めていない自縄自縛と頼りにならない鈍重な政権により、自分の手で自らを苦しめる「第二の失われた何十年」に足を踏み入れてしまうかもしれません。
景気や社会情勢に大きく左右される広告業界、その中に含まれるWeb制作やマーケティング分野も、時代の大きなうねりから逃れることはできません。
今、どう動くか。何を選ぶか。主体的に考え、打ち手を講じるだけでなく、実行に移さざるを得ない。過去最大級の正念場を迎えている。それが、一業界人としての直感です。
実業、そしてその先へ
荒波に揉まれたくないなら、実業という碇を下ろしましょう。広告となるWebサイトを作ったり、広告出稿だけに留まっていては、いつまでも「虚業」の域を出られません。お客様の役に立つという、地に足のついた「プラスアルファ」が必要です。
例えば、システム開発に強みがあるなら、Webアプリや業務系システム、あるいはECサイトに特化する選択肢も考えられます。BtoBや特定の業種、地域に軸足を置く戦略も、これからの時代にフィットします。また、AIの力を借りながら、半ば人海戦術的にコンテンツマーケティングやSNS発信を強化するという手段も有効です。「面倒臭さ」を代行するという価値は、重みを増すでしょう。
BBNは、こうした選択肢の中から「カスタマーサクセス」や「問題発見」に注力して、Webサイト制作という枠にとらわれず、クライアントの事業そのものに深くコミットする道を模索しています。Webサイトを作るという小さなきっかけから、「えいやっ」と事業全体へ影響を及ぼせたら、もう「虚業」とは言われないでしょう。
可能ならその先にある未来、新たな社会の創造までとも考えていますが、現在着実にご提供可能なのはWebサイト制作の範疇です。余裕がない厳しい状況でも打開のきっかけとしていただけるように、月額制でコストを抑えたオファーをご用意しています。
小さな投資がビジネスや経済を刺激する種火となるよう、尽力してまいります。どうぞ気軽に、ご相談ください。
おしまいに
楽観視できる状況ではないからこそ、有効で手軽に選べる選択肢でありたいと考えています。月額1万円で、サーバ代も制作費も全て込み。パターンオーダーからビスポークへ至るWebサイト制作をご提供しています。
少額投資でも成果が出やすいよう、無理に攻めるのではなく、機会損失の回避や高速表示、指名検索に重点を置き、必要に応じてアクセスデータを活用しながら、PDCAサイクルやOODAループを組み合わせた施策提案も行っています。
輝かしい、新しい朝が来るように。BBNと一緒に、Webサイト制作やWebマーケティングに取り組んでみませんか?
また、もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら