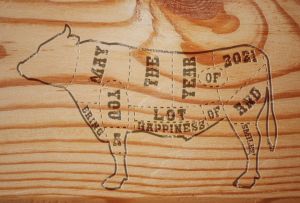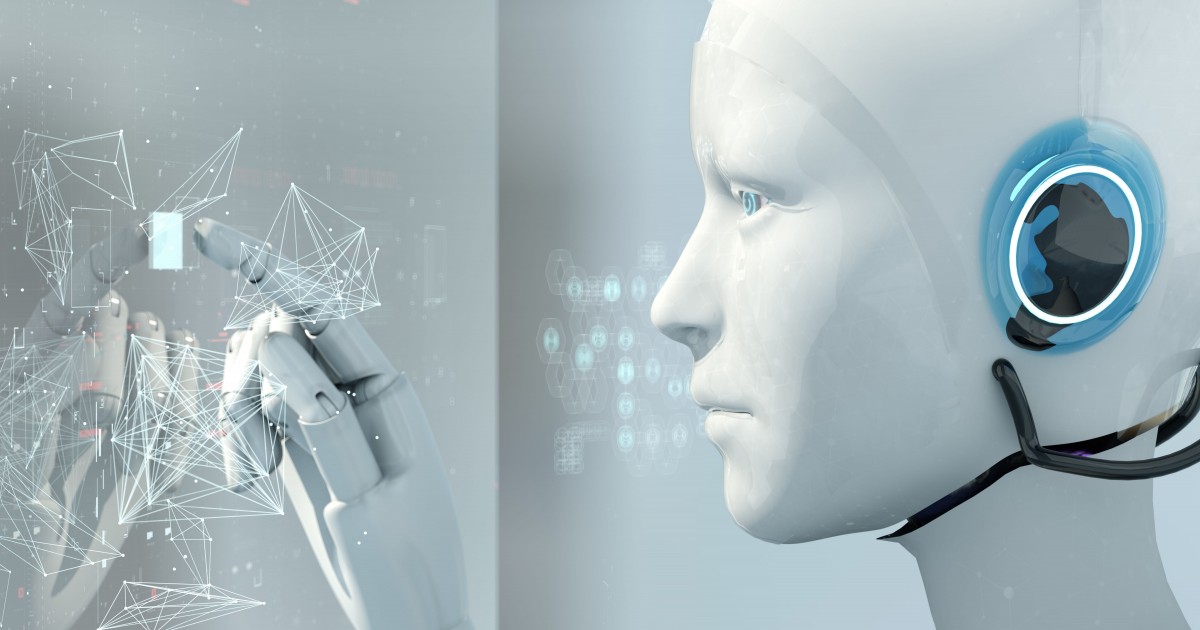月刊BLUEBNOSE 2025年08月号(#20)『ブランディング×悪酔いは、地獄の始まり』
ぜひ、オウンドメディアの記事と合わせて、ご活用ください。
最近なんとなく、周囲で「ブランディング」に注目が集まっているような気がします。そこで、先日オウンドメディアでは『ブランディングは、形から入るな』という記事を公開しました。
ブランディングに関する基本的な考え方や、最初に注意しておきたいポイントなど、エヴァーグリーンな内容を中心にまとめています。ただ、オウンドメディアでは取り上げにくく、あえて触れなかった要素もまだあります。
それなら、メール配信型のこちらで取り扱えばいいということで、先日のオウンドメディアに引き続き、テーマは「ブランディング」です。
厳密にはブランディングというよりは、ファンや共感を軸にしたブランディングの「運用フェーズ」やコミュニティの形成に関する注意点です。それらも広義のブランディングということにして、大きな声では語りにくい部分を深掘りしていきましょう。
ネーミングも含めて、やり過ぎは控えたい
非常に個人的な意見というか、感覚に基づくモノなので客観性に乏しい偏見ですが、企業名やブランド名、商品名といったネーミングの段階からカタカナや横文字をふんだんに盛り込んだ、カッコつけ過ぎの「看板」を見ると、それだけで鳥肌が立つような気がします。
自らの厨二心というか、周りのことなんか一切気にしていなかった幼い頃を刺激されるような気がして、あの頃の気恥ずかしさを思い出してしまうというか、共感性羞恥に苛まれてしまいます。
TPOも弁えず、大きな声で好きなアニメやヒーローの固有名詞を叫んだり、己の未熟さも顧みず、浅い知識をひけらかしたり、陰謀論やスピリチュアルの世界へ突っ走ってしまったり。「自分は特別で、他人とは違う」と思い込みたかった時期に思いを馳せてしまうので、「カッコいいね」とか「イケてるね」と素直に受け取れない自分がいます。
また、一社会人、特に横文字の多そうなITやWeb業界に身を置いていると、「看板」が立派であればあるほど、あるいは大層なネーミングを採用しているところほど、「看板」に対して「中身」が伴っていない傾向がある、という一般法則も見えてきます。
ブランドの雰囲気作りや世界観を構築するために、ネーミングやタグライン、フレーバーテキストは非常に重要ですが、その段階で「自分たちの世界」に振り切ってしまったり、過大な「虎の威」を引用して引っ被ってしまうと、それがかえって「まだその世界に染まっていない」巷の一般人を遠ざけることになりかねません。
例えば、イーロン・マスクの介入によって、TwitterからXへリブランディングした事例があります。
ご存知のように、イーロン・マスクはテスラ社やスペースX社など先進的な企業をいくつも所有していますが、興味関心の中心に「宇宙」が据えられています。
青い鳥から、急に宇宙を意識した未知数への転換を果たし、Xへ搭載されたAI、GrokはGをモチーフにしたロゴマークからして宇宙っぽい印象があり、入力待ちのアイドリング画面は天の川や流れ星っぽい意匠も採用されています。
この方針転換や、宇宙に振り切ったブランディングは、既存ユーザーが折れて受け入れているだけであり、本来なら性急過ぎる打ち出し方と言えるでしょう。誰も彼もが、イーロン・マスクの考え方や趣味を受け入れているとは限りません。
文脈や背景がユーザーに共有されていないときに、作り手だけの“ノリ”や“世界観”を押しつけると、ファンの共感どころか反発を生む危険性がある、という好例でしょう。
何事も、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」であり、「伝わらなければ存在しないのも同然だ」と脚色や演出で大きく見せたいのもよく分かりますが、加工し過ぎ、盛り過ぎはやはり敬遠されてしまいます。「腹八分目」という程々が見極めにくいブランディングの世界では、「ちょっとダサい」ぐらいが程良いのではないか、と個人的には思います。
そのブランドが取り扱う商品やサービスにもよりますが、利用者の生活や日常に持ち込まれるモノであれば、あまりにも「異質」なものは馴染まないし、避けたくなるのが自然です。普段の延長にありながら、独自の「違和感」を秘めている。
それぐらいの塩梅が、ベストじゃないでしょうか。もし、Googleがグーゴル(googol)=10の100乗という社名の元ネタと同じ綴りを採用していたら、早々に転けていたかもしれません。
綴り間違いをしたおかげで、身近な存在になったとすれば「怪我の功名」でしょう。「ちょいダサ」をあえて狙った巧妙なブランディングだった可能性も捨て切れませんね。
気合いが入り過ぎたファンも、ちょっと苦手
これも、かなり個人的な感覚というか偏見なんですが、いい歳した大人で「ディズニーが好き」と公言する人や、USJなどのテーマパークの「年パス」を買って、何度も訪れる人に対しても、その情熱は素晴らしいと思うものの、妄執性に若干引いてしまうことがあります。
特にディズニーは、物語に触れた経験が少ない幼少期には素晴らしいコンテンツに映りますが、年齢を重ねて様々な作品を知れば知るほど、「都合のいいお伽話」ではないかと思わされる瞬間があります。
それは何もディズニーに限った話ではなく、スタジオジブリ作品でも、大人になってから振り返ると、「それはどうなんだ?」と思うシナリオやキャラクター描写があると気付かされますし、大人の目で見ると現実との乖離を感じさせる部分が目立ってしまうのかもしれません。
「予定調和的な展開」や「都合のいいハッピーエンド」もディズニーらしさであり、それが魅力でもあるのですが…。
だからこそ、「ディズニーが好きな自分が好き」という側面も少なからずあるような気がして、その没入度合いや忠誠心には、正直少し怖さを感じてしまうこともあります。
信仰にも似た熱量は素晴らしいなと思う反面、特定の世界に染まりきってしまうと、外から見る人にはそれが「異質」に見えてしまうーーそれは、ディズニーに限った話ではなく、多少息の長いコンテンツやブランドに対するファンコミュニティや、熱量全般に言えることなのかもしれません。
また、先にそのコンテンツに触れている先輩がいたり、そういった人たちが教え魔になったり、あるいは新参者を厳しくチェックする審査官になったりして、コミュニティ内での上下関係やヒエラルキーを形成してしまったり、コミュニティの同質化や硬直化を誘発してしまっていると、尚更入りにくさは向上します。
新規参入のハードルを上げてしまうと、ファンコミュニティもブランドの土壌も細ってしまい、気軽に近付けない、カルト的な集金装置になりかねません。
歴史の長いコンテンツやブランドほど、自ら間口を広げ、新規参入しやすいよう積極的に取り組むのは、そういった現象の回避を狙っているのでしょう。新しい人や風を取り込んで風通しを良くし、コミュニティの若返りにも繋げる。
気合の入ったファンほど、ブランドのために一歩引く姿勢が求められるのかもしれませんね。
ブランディングに多少の「酔い」は不可避
ブランディングを仕掛ける側も、ブランドを支持するファンの側も、余りにも浮世離れしていると近寄りがたいとお伝えしてきました。ただ、ブランディングに取り組む以上、ある程度は雰囲気を作ったり、気持ちを高めたり、ブランドの世界観に入り混む必要があるというのも、事実です。
映画やドラマ、舞台などの「作り物の世界」に入り込み、板の上で演技をするには、本番と日常を切り替える「スイッチ」が必要でしょう。プロポーズや告白といった大事な場面でも、シチュエーションの力を借りたり、多少の脚色が欲しくなるはず。
人目を引くビジュアル、心をくすぐるネーミングやコピー、フレーバーテキストを考える際に、素面のまま、「いつもの自分」では中々難しい。日常の世界を抜け出して、お祭りのような特別な「ハレ」の世界へ、普段とは少し違う自分になるためにも、多少の「酔い」は必要不可欠です。
つまり、ある程度「作られた」状態がなければ、ブランディングや創作行為は成り立ちません。ただし、前後不覚になるような深酒や、翌日や翌々日まで響くような悪酔いでは、仕事として成り立たないのでNGです。
戯作三昧の境地で、無我夢中に没入するのは個人の自由ですし、その喜びや楽しさが格別なのもよく分かりますが、それを「見せつけられる」周囲にとっては、迷惑でしかありません。
「自分勝手に楽しんじゃって」と笑顔で言いながら、内心では早くその場を離れたいとか、関わりたくないと感じているのでは。
やはり、「やり過ぎ」は禁物。ブランディングのためとはいえ、クリエイティブも含めて尖り過ぎてしまうと共感性羞恥を誘ったり、「気持ち悪さ」へと転じる恐れもあります。
当事者やファンには心地よくても、外野からは「鼻つまみ者」になってしまいます。そうなる前に、冷静な判断ができるレベルで踏み留まることが大切です。
熱狂と客観視の両立を
ブランディングやファンコミュニティの形成、運用において、独自の世界観に入り込み、作り込むことはとても重要です。ただ、それと同じぐらい、「周囲からどう見られているか」という客観視や、データに基づく冷静な市場分析も不可欠です。
中に入り込めば入り込むほど、信仰は深まりますが、それに反比例して視野は狭くなりがちです。妄執的になり、自分たちの価値観や世界観へ過度に固執してしまうリスクもあります。
そんな世界に、たまたま近くを通りかかった人が「入ってみよう」と思うでしょうか。熱狂や同質性が過剰に出てしまうと、「これは自分に関係ない」「ちょっと怖い」と距離を置かれてしまうのが普通の反応です。
だからこそ、ブランディングを仕掛ける側や熱心なファンこそ、自分たちの姿が「外からどう見えているか」を、冷静に判断する必要があります。
独自の世界観へ深く中に入り込むと同時に、素早く俗世間へ戻って来る。その切り替えの速さや、反復運動の柔軟さ、的確な情報収集と状況判断が、ブランディングには求められます。
これからブランドに触れてくれるかもしれない人を遠ざけないために。新規参入してくれる人を選び過ぎないためにも、入り口はできるだけ広く、安心安全に。そして、奥行きは深く、敷居も可能な限り低くしておくことが、健全なブランディング、ファンコミュニティの発展には不可欠です。
より強固なブランドを目指すからといって、過度の深酒や悪酔い、本格的なトリップやトランスを求めてしまうと、いずれブランドもコミュニティも、衰退を免れません。
「ブランドの終焉」という地獄を避けるためにも、悪酔いややり過ぎは厳禁で。
自然と偏るから、積極的に嫌われなくていい
ブランディングやマーケティングに力を注ぐと、「万人に好かれる」はどうしても難しくなります。「誰かに選ばれやすくなる」ことと、「全ての人に選ばれる」ことは、同時に成立しないので、選ばれるために工夫を凝らせば凝らすほど、消費者の中には「好き嫌い」や「合う合わない」といった自然な選択圧が発生します。
ただし、それはあくまでも結果論です。自分たちから積極的に「この人たちには選ばれなくていい」と切り捨てたり、「遠ざけられる理由」をわざわざ作る必要はありません。
先鋭化し過ぎれば人を遠ざけますし、世間が眉を顰めているようなジャンルや言動に自ら近付いて仕舞えば、それだけで選択肢を狭めてしまいます。
わざわざ自分たちから、嫌われる理由を増やさなくていい。ブランディングを仕掛ける側が「誰を選ぶか」を決める必要はなく、選ぶのは常に生活者や消費者です。その良し悪しや、自分の好みに合うかどうかを、彼らが勝手に見極めます。
最初の選択肢で無駄に損をしないためにも、ブランディングには冷静な客観視や、市場調査、生活者に対する共感や想像力が欠かせません。
浮世離れした世界観を構築するのは結構ですが、「普通」や「俗世間」の感覚を、きちんと把握できていますか?
ブランディングは二人三脚で
ブランディングには、高度な自己理解や自己愛と同時に、鋭い客観視や他者とのコミュニケーション力が求められます。「自分」を100%で見つめながら、「他者」が受け取りやすいよう、相手の視点を100%で捉えるのは、まるで右と左を同時に見るような難しさがあります。完全な自己完結は、簡単ではありません。
だからこそ、一人で抱え込まず、我々と分担してみませんか?
アナタはアナタのブランドに全力を注ぐ。我々は、世間や市場、見込み顧客への見せ方、伝え方を全力でサポートする。その二人三脚で、より良いブランディングを目指しましょう。
少しでも気になることや興味がありましたら、いつでもご相談ください。
また、もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
さて、月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら