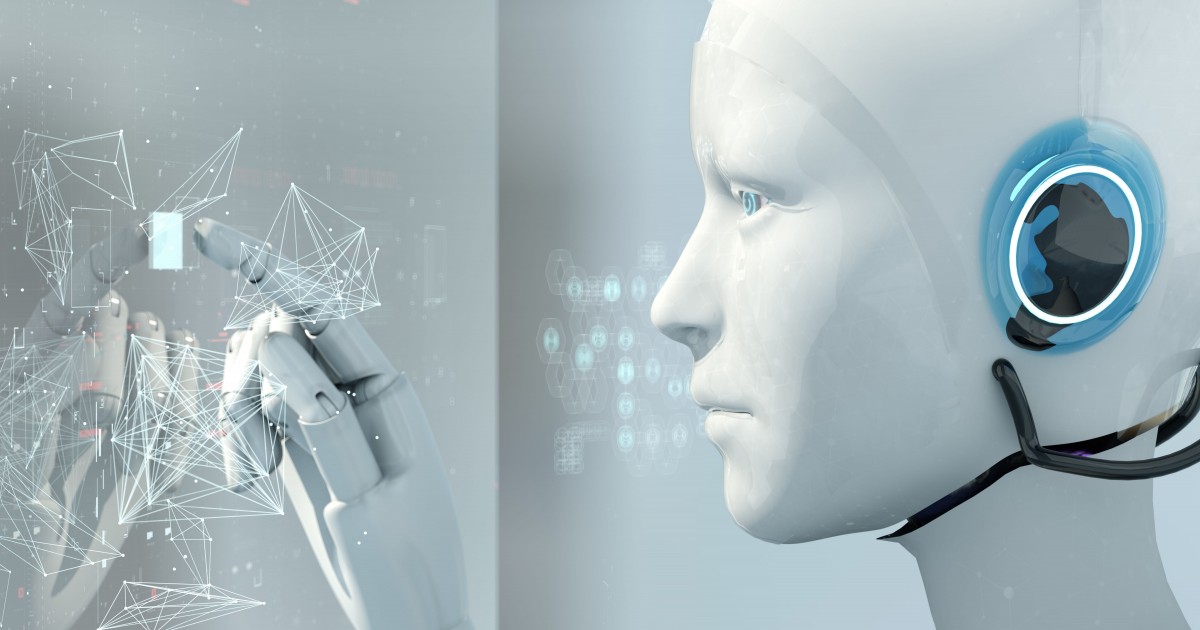月刊BLUEBNOSE 2024年12号(#12)『伝えたいヒトもココロも、諸行無常』
受け取る相手、トレンドの変化について筆者なりにまとめてみました。
何を変えて、何を「変わらないもの」とするか。少しでも参考になれば幸いです。
11月の最終週頃から毎週のように、12月に入ると毎日のように「いつの間に」と残りの日数の少なさに驚きながら、「今年もそんな時期か」と何となく「繰り返し」を痛感する季節ですね。そして年が明ける頃には、「もうそんなに経った?」と時の積み重ねに恐れ慄いたり......。
数年ぶりに地元へ帰省したり、一年ぶりや半年ぶりに実家の両親と顔を合わせると、その変貌ぶりに驚いたり、移ろいゆくもの、失われていくものに想いを馳せてしまうのも、年末年始の今頃に特有の現象でしょうか。
部屋の片隅に積もった埃を払い、頑固な油汚れやカビと闘いを繰り広げ、住まいを払い清めて新年を迎える準備をし、心の中のモヤモヤや煩悩は、除夜の鐘で払ってもらうこの国の習俗に、諸行無常も感じてしまいます。
毎年同じことを繰り返しているように見えても、螺旋のように少しずつ変わっていく。変わらないものなんて何処にもないんだなと痛感する時期ですが、そういう暮らしやリアルから遠いように思えるデジタルな分野、精神的な分野でも、実はあらゆる物が「無常」だったりします。
永久不変の「法」の領域に至っていない要素、伝えたい相手やその心やトレンド、勘所について改めて整理してみましょう。"Contents is King."だけれども、容れ物の影響が非常に大きいという話を公開したばかりですし、コンテンツからは遠いけど、影響力が非常に大きい外側の部分、年輪で言えば表皮に近い部分の話を取り上げてみます。
意識高い系やWoke、マスコミが好意的に取り上げるものが嫌われつつある
まずは、国内外で目立った選挙をいくつか振り返ってみましょう。
6月20日告示、7月7日が投開票だった東京都知事選、10月15日公示、10月27日が投開票日だった衆院議員選挙、11月5日が一般投票だった米大統領選挙、10月31日告示、11月17日が投開票日だった兵庫県知事選挙辺りと、それらにまつわるマスコミ報道へ目を向けてみると、見出しのニュアンスが何となく伝わると思います。
日本国内のマスコミとしては好意的に報道されていた候補者や、意図的に作り上げられていたイメージを払拭するような結果、マスコミの思い違いに冷や水を浴びせるような結果が、ほぼ「ゼロ打ち」で示された選挙もありました。
兵庫県知事の出直し選挙に至っては、圧倒的な民意が示されて再選が決まった後、地上波テレビや新聞紙面上でSNSを悪者にする論調が展開されたり、問題の多い百条委員会や告発文書を元に、なおもパワハラの有無や責任追及が続いたりしていましたが、肝心の公用PCのデータが一部公開された途端、その論調は一気に静まり返ってしまいましたね。
また、日本国内の報道では直前まで「ほぼ均衡」のように伝えられていた米大統領選挙も、蓋を開けてみればトランプ氏の「ほぼ圧勝」と言える結果であり、もっと先まで最終結果が判明しないかとも思われましたが、翌日までには揺るぎない結果が示されています。
"トランプ氏が勝った州は大学進学率が低く、ハリス氏が勝った州は高い”とリベラルの論客が評していたり、ハリス支持者は『ガラスの天井』だの、『性差別や人種差別に負けた』と言った意見を述べているとか。
日本国内のマスコミや、米国の民主党、ハリスの支持層がそのまま意識高い系やWokeと結び付くとは言いませんが、少なくとも、大衆はマスコミの思惑通りに反応しなくなったとは言えるでしょう。
また、『アサシン クリード』の弥助問題や、マーベルのMCU、ディズニー映画をはじめとする、いわゆる「ポリコレ」や「DEI」に配慮したエンタメ作品が、興行収入的に苦戦していたり、環境保護活動や動物保護団体の過激化が目に余るようになり、一部からは「テロリスト」と称されるようにもなりました。
環境問題へ目を向けると、主に欧州自動車メーカーが肝入りだったEVも苦戦しており、日本国内では再生可能エネルギーは本当に環境負荷が少ないSDGsな電力なのか、疑問符がつくようにもなっています。自然本来の姿を過度にありがたがり、外来種であるジャンボタニシを使った栽培や無農薬、有機栽培が従来の慣行農業よりも素晴らしいものだと決めつける考え方にも、様々な異論、反論が飛び交うようになりました。
日本国内の創作物とマスコミを巡る問題としては、芦原妃名子さんの『セクシー田中さん』のドラマ化や脚本を巡ったトラブルもありました。批判の渦中にあった「日テレ」は『24時間テレビ』の寄付金着服問題があったにも関わらず、対処法が曖昧なまま今年も例年通りに『24時間テレビ』を放送していましたね。
マスコミが作り上げようとするものや、マスコミが好意的に受け止め、流布しようとしているイメージに対して、素直に受け止めるのは難しい時代となっています。マスコミの意図に沿う演出や、彼らが好む論調、単純でただ「映える」ことだけを狙った演出は、歓迎されない時代、眉に唾を付けないと受け取れない時代へと、変化しつつあるような気がします。
歓迎される表現やトレンド、セオリーも変化する
これまで「良い情報発信」の参考として、マスコミや映画制作は優れた教材とされてきましたが、今はその存在、価値が大きく揺らいでいます。今もなお、マスコミや大手広告代理店の手法が通用するのであれば、地上波テレビの視聴率はもっと上がるでしょうし、新聞も雑誌ももっと売れて然るべきですが、人口減を上回るスピードで廃れ、コンビニの売り場面積も減少する一方です。
人文学系の古い翻訳や、文豪の古典的名作の冒頭で「現在では差別的で不適切と思われる(中略)原文のままといたしました」のような注意書きが添えられていることがあります。明治や大正、昭和初期や平成と令和の現在とで、受け入れられる表現や価値観が大きく異なるのは言うまでもありませんが、この十年や十五年ほどのスパンでも、押さえておくべきトレンドやセオリーが変化しています。
例えば、ブログを使ったマーケティングやブランディングとして、運営者自身をその分野のエキスパートと位置づけ、読み手に教えるスタイルを是とする風潮が確かにありました。自分たちには一日の長があり、記事を読む人は何も知らない素人であるという前提に基づき、「教えてあげる」という姿勢が正しいとされていました。実際に、それを推奨するような教本も沢山ありました。
しかし、筆者個人の感覚では、当時からそのような「上から目線」は好ましくないのではと感じていました。現在、SNSの反応を鑑みるに、こうした態度や姿勢はやはり歓迎されていないように思います。
ゼタバイトの時代になり、大量の情報が日常的に浴びせられるようになった今、書いてあることや行間だけでなく、そこに込められた意図や、書き手の姿勢や態度までもが、明確に読み取れるようになってきました。
普段の振る舞いや言動も含めて総合的に判断されるため、読み手は「教え込まれるなんて、ゴメンだ」とか「この人はどうも信用ならない」と判断した時点で、コンテンツへ触れる前に「回れ右」であっさりと離れていくことも珍しくありません。
十年前や十五年前に推奨とされていたスタイルやセオリーですら、取扱注意の分野です。受け手自身や受け手を取り巻く環境、トレンドの変化を無視して自分たちの発信方法や中身だけを気にしたところで、「(真意まで)受け取ってもらえるか」は微妙なところでしょう。
受け手に負担をかけるのは、不易流行でNG
トレンドやセオリーがどんどん変化し、「諸行無常」であるという話題を繰り広げていますが、情報を発信する際、受け取る相手に面倒や手間といった負担をかけるのは、どんなに時代が変化したところで絶対的に「NG」な行為です。これはもはや、「無常」とは無関係な「法」の域に至った不滅のルールです。
情報発信というのはある意味、キャッチボールみたいなものなので、一度に二個も三個もボールを投げても全部は受け取ってもらえませんし、相手の胸に向かって投げないと、受け取る相手に負担をかけることに繋がります。キャッチボールなら、「ちょっと動けば、取れるでしょ」は許されるかもしれませんが、伝える相手が、必ずしもそんな甘えが許される関係とは限りません。
人生の大先輩かもしれませんし、逆に力が弱い未就学児童かもしれません。顔見知りではない、初対面の人である確率が高いでしょう。目が合っただけの人に、何の配慮もせずに取りにくいボールを投げてもいいと思いますか? 相手は一切動くことなく、自然にボールを受け取れるように投げる。礼儀として、相手に甘えないことがスタートラインでしょう。
ここで更に注意したいのは、「音」と「繰り返し」。
読み上げを全く考慮しないテキストであれば、「どう聞こえるか」や「繰り返した時の印象」なんて気にする必要はありませんが、WebCMやスクリーンリーダーなどのインクルーシブな要素も考慮するなら、「音」と「繰り返し」も気にかけるべきです。
例えば、耳で聞いただけでは意味や文字が思い浮かばない表現がある場合、「どういう意味?」とか「どんな字?」と余計な負担をかけてしまいます。同音異義語が多く、イントネーションでニュアンスが千変万化する日本語の場合、特に重要なポイントでしょう。
また、誰かが読み上げる場合は、聞き取りやすさもポイントとなってきます。「今、なんて言った?」と負担をかけてしまうのも、良い印象は与えません。
何度も何度も耳にするCMやジングルの場合、映像が見えていない時でも嫌な印象になっていないか、じっくりチェックされることをオススメします。動画再生サイトやラジオ等で流れた時、意外と悪い印象として刷り込まれているCMや音楽は、かなりあります。有名ブランドのCMでも、映像を伴って初めて悪い印象を拭うことができたものも少なくありません。
自分たちは理解できる「造語」や、まだ一般に浸透しているとは言えない略語や略称についても、受け手に負担をかけることになっていないか、自分勝手になっていないかを、一度立ち止まってみることをオススメします。
あなたは発信することに精一杯で、投げたボールは受け取ってもらえるはずと意気込んでいますが、受け取る方は、無理に付き合う義理も義務もありませんから。相手から進んで受け取ってもらいたいなら、あなたが受け取りやすくなるよう、工夫を凝らしましょう。
ストックの情報は、イヤミのない他所行きスタイルで
SNSのようなフローの発信でも、内輪しか見ていない発信を見かけると隠された同調圧力や太鼓持ちめいた雰囲気、受け手に対する愛情ではなく甘えを強く感じてしまい、距離をとりたくなりますが、ブログ記事などのストックの情報は、誰が目にするか分からないので、公共性を意識した他所行きの装いが無難かと思います。
特定の界隈でしかチヤホヤされない「イヤミ」を含んだ他所行きだと逆効果なので、イデオロギーや宗派性はできるだけ控え、どこに出しても問題ないような無難な感じがベターでしょう。無難さを軸に、個性や遊びを加えるのは問題ありません。
SNSでのフローの発信は、特定の空間、例えば教室や部室、あるいは会議室である程度同質の相手、顔が見えている相手へ気を許した上で発信されるものだとすれば、ストックでの発信は完全に屋外、都心のメインストリートや記者会見の場で発言するようなものと考えると、どれぐらいのバランスが良いか、何となくお分かりいただけるかと思います。
本当は、フローの発信でも公共性を意識したスタイルで発信されるのが、オススメではあります。炎上騒動や何らかのハラスメント、裏アカウントの流出や情報開示請求といった展開の抑止にも繋がるとと思うので。
伝えたい相手も、背景も変わっていく
あなたの伝えたいことや伝えたい想いがどれだけ強く、素晴らしいものであっても、相手の事情や相手が置かれている環境や背景に、「いつまでも変わらないままでいて」とお願いすることはできません。
情報に対する向き合い方の変化や、マスコミが「マスゴミ」や「オールドメディア」と呼ばれて相手にされなくなりつつある変化を加味せず、今までと同じスタイル、同じ味付けで受けてへデリバリーすることはできても受け取ってもらえない、味わってもらえない可能性が高いでしょう。
未読スルーやブロック、ミュートといった選択肢もある世の中で、伝え方や伝える相手に合わせた表現、内容を考えないと、「届いているのに反響がない」ことになりかねません。
物理的なものとは疎遠なはずのノウハウやトレンド、セオリーも「諸行無常」。変わらないと思っていたもの、変わらないと信じていたものが変わっていってしまうからこそ、中学や高校の3年間、あるいは大学の2年間や4年間という期限が尊く、また「変わらないもの」を取り上げた歌がグッと来る訳で。
適切なスタイル、適切な届け方は時代とともに、あるいは月日とともに変化しています。あなたの「変わらない」伝えたい想いを、しっかり届けるにはどうすべきか。伝えたい相手やトレンドにも、しっかり気を配りたいものですね。
おしまいに
マスコミとSNS、あるいはマスコミと大衆がどんどん離れつつある昨今、「伝わりやすい」のトレンドやセオリーも、技術と同様に秒進分歩の時代です。簡単には「変わらない」と思っていると、足元を掬われてしまいます。
BBNは、変化を見極めながら、情報発信やWebサイト制作に向き合っています。
何が変わらなくて、何が変わるのかを考え続けている我々と、Web制作やWeb活用に取り組んでみませんか?
また、もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら