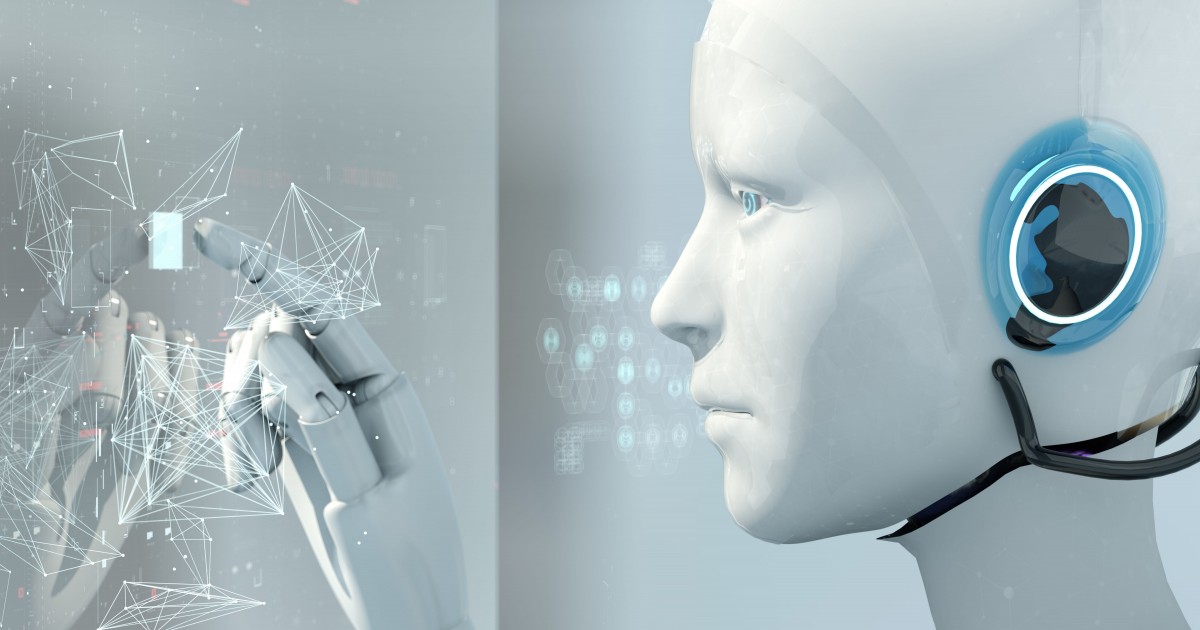月刊BLUEBNOSE 2025年02月号(#14)『現場(カオス)の時代』
個人的に引っかかっている意見表明、批判に関する漆塗りなので、少しでもご理解いただけますと幸いです。
去年の年末頃に関連スピンオフ作品が劇場公開され、2012年に「Final」と銘打って劇場公開されたにも関わらず、2026年公開予定の新作まで情報解禁された『踊る大捜査線』シリーズですが、年末年始に地上波での再放送とかもしてましたね。私もつい先日、例のセリフが脳裏をよぎったのでネタとして使わせてもらいましたが、母体のフジテレビが揺れているのでどうなるのか、ちょっとだけ気になりますね。
先月の記事内でも拾わせていただいた「事件は会議室で起きてるんじゃない! 現場で起きてるんだ!」の「会議室」と「現場」のモチーフというか、比較がかなり興味深かったので、他のメディアでは取り上げにくいお話として、改めて深掘りしようと思います。
こちらのメディアで取り上げるお話としては、何となく方向性が固まってきた気がするので、この手のお話は一旦一区切りするつもりで、早速本題へ入りましょう。
会議室と現場
まず、『踊る大捜査線』(以下:『踊る』)の骨子を振り返ってみましょう。このシリーズでは、として警視庁 vs 所轄として警察機構におけるエリートと叩き上げの対立軸があり、織田裕二演じる青島俊作と柳葉敏郎演じる室井慎次が、立場の違いを超えて相互理解を深めながら、どちらも出世しないと、警察は変わらないという話に発展していくというのが基本線(だったと思います)。
テレビの連ドラから続く象徴的なキーワードとして、劇場版第一作目で「会議室」と「現場」にスポットが当てられたと思われます。
この「会議室」と「現場」を掘り下げる補助線として、『高学歴社員が組織を滅ぼす』(上念司著 PHP研究所)と
『スルメを見てイカがわかるか!』(養老孟司 / 茂木健一郎 共著 角川oneテーマ21)も添えておくと、非常に示唆的なものが見えてきます。
「スルメ」は一度死んでデータになった存在であり、その後が予測しやすい「死んだ問題」の象徴です。その一方、「イカ」は生きた状態でその後が予測困難な「生きた問題」を示しています。受験勉強を勝ち抜いてきた人「会議室」は「スルメ」と向き合って答えを導くのが得意であり、「現場」は日々「イカ」と向き合っているような状態と言えます。
この発想を広げると、スルメは「閉鎖系」、イカを「開放系」と捉えることもできそうです。閉鎖系では外部の影響を遮断してシミュレーションしたり、モデル化もしやすいですが、開放系では外部の影響を受けて変化してしまう複雑な要素を含みます。つまり、「会議室」は決定論的であり、線形的な問題解決を志向しがちですが、「現場」は非線形で創発的な要素を扱わざるを得ない量子力学系とも言えそうです。
「会議室」はクリーンかつ極めて脳的な環境であり、脳が予測困難な「細菌」や「虫」はフィルタリングされて存在しません。「現場」は砂埃が舞う屋外であり、外界の多様な影響を受け続ける、カオスそのものの環境です。
こうした対比を見ていくと、なぜ『高学歴社員が組織を滅ぼす』のかや、『申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。』(カレン・フェラン著 大和書房)や、『「経営コンサルタント業」の倒産が過去最高』だったり、欧米も含むコンサルティングファームでリストラが進んでいるのかも、なんとなく見えてくるのでは。
「会議室」は意識が高く、理想的で煌びやか
筆者の偏見が相当含まれていますが、様々なものを「会議室」と「現場」で振り分けた時、何となく「人工的」で加工度合いが高い観念的なもの、煌びやかで上流階級と親和性が高そうな「高尚なもの」が「会議室」。「現場」は、それらとは真逆で加工度合いが低めの生っぽいものや、何となく匂いがキツそうな「クセの強いもの」や、ちょっぴり不良めいた男臭いものが振り分けられそうなイメージです。
「会議室」の方が全体的に洗練されていて都会的かつ進歩的であり、「現場」は野暮で田舎くさく、古臭さもある保守的なもの、という傾向があるような気もしますね。
『踊る』でも描かれていたように、「会議室」は、知的エリート的な官僚や文官を連想させます。これは、マルクス的な経済観や歴史観、旧来のエスタブリッシュメントな層やウォール街、さらにはGAFAMに代表されるIT系文化とも親和性が高い印象です。アメリカで言えば民主党支持層、またはメインストリームの文化とも結びつきそうな気がします。
「現場」はより体育会系的な武官的価値観を持ち、書籍や座学よりも経験と実践を重んじる文化と結びつきそうな印象です。アメリカで言えば共和党、特にドナルド・トランプ支持層や、サブカル系の文化との親和性が高そうで、マルクス経済ではなくケインズやシュンペーター、スティグリッツ的な考えを支持し、MBAよりも経済学のPh.D.に見解を求めるような気もします。
つまり、「会議室」は左派、リベラル的なイメージを象徴し、「現場」は右派、保守的な印象を端的に表現したワードとして捉えることも可能ではないか、という偏見です。これまで何度か語ってきた、欧米政治のトレンド変化や、ドナルド・トランプ再任を見据えた「トランプ・シフト」によって生じている反リベラル、反Woke、反DEI、自国ファースト、保守回帰について、「会議室」と「現場」のモチーフを借りながら説明することも可能ではないか、という発想です。
大統領選挙で民主党陣営、特にカマラ・ハリスがなぜ敗北を喫したのか。環境保護活動や、過激なヴィーガン運動、ポリティカル・コレクトネスといった「目覚めた人たち(=Woke)」が忌避される理由や、移民政策の失敗が指摘され、自国ファーストへの回帰が目立つようになった背景も、『踊る』で描かれた「会議室」を思うと、何となくお分かりいただけるでしょう。
ペーパーワーク中心で、行間やビッグデータを取りこぼしやすい
「会議室」の何が問題なのかは、『踊る』だけでなく「象牙の塔」や「頭の硬い上層部」を描く作品を見れば、お分かりいただけるでしょう。また、ご自身の職場で、日々感じる部分もあるかもしれません。
彼らは「(チーフ)オフィサー」です。その役割は、現場で採取されたデータやサンプルを元にした統計や、末端の人員が作成する書類を参照し、全体を俯瞰して戦術や戦略を指示することです。組織が大きければ、それぞれの文書を持ち寄り、「会議室」で議論を戦わせるのが仕事です。
それが彼らの職務である以上、時事刻々と状況が変わる現場や、その予測不能性、書類や統計に表れないニュアンスまで深く読めと求めるのは、そもそも筋違いです。だから、「現場」と「会議室」の両方が存在し、相互に補完し合うのが理想です。
しかし、採取できたデータや書類、「スルメ」だけで考えてしまうと、生存者バイアスやいわゆる「事後孔明(事後諸葛亮)」により、「イカ」の生態や特徴を正確に把握できず、因果関係や相関関係を見誤ることもあります。
例えば、ティラノサウルスのイメージが『ジュラシック・パーク』のようなカッコいい暴君として描かれていたかと思えば、巨大で太ったヒヨコのような姿ではないか、という議論も度々起こっています。新たなイメージ図が登場するたびに残念な気持ちになり、「あの頃のティラノサウルスを返せ」と思う方も沢山いらっしゃるでしょう。
なぜそんなことが起こるのか。その答えは簡単で、「スルメ」と「イカ」は別物であり、正確な情報が欠落してしまうからです。これを「化石」と「生きていた頃のティラノサウルス」に置き換えても良いでしょう。時代を超えても残りやすい部分(骨格などの硬組織)と、時間と共に腐り落ち、分解されてしまう部分(筋肉や皮膚などの軟組織)とでは、後から得られる情報に大きな差が生じます。
現代でも、骨格から元の動物やその肉付きを想像するのは非常に困難です。司法解剖でも、何が死因となったかを特定することは可能ですが、なぜそうなったのかを予測するのは難しい問題です。解剖学を専門とする養老孟司氏が「スルメ」から「イカ」のことが分かるのかと疑問を呈したのは、彼の死生観だけでなく、豊富な経験に基づいていると言えるでしょう。
養老氏は解剖学者であると同時に医者でもありますが、ご自身は医者嫌いであることも知られています。彼は健康診断やレントゲンなど、その瞬間を一時的に切り取ったデータ、つまり「スルメ」から今生きている人間の状態をどれだけ正確に診断できるのか、というやや偏屈に思える指摘もされています。
「現場」と「会議室」の間で発生する齟齬も、この「イカ」と「スルメ」に通じるものがあります。特に、「イカ」が持つ非線形で予測困難な複雑系の性質と、「スルメ」のような線形的で理想論的な閉鎖系の性質という違いが、大きな要因でしょう。トップダウンとボトムアップの双方向で正確な情報が行き交う環境を整備したとしても、視座の高さや属する「系」の違いを埋めるのは簡単ではありません。
ちなみに、「会議室」と「現場」の嗜好性(や志向性)については、前述の通りです。
VUCA、OODA、STEAMは「現場」寄り
予測困難な現代を表す表現として、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った「VUCA」という言葉があります。2010年代にはビジネスでも用いられるようになったので、「また、それか」と思う方もいるかも知れません。
そんなVUCA時代に適応するフレームワークとして、Observe(観察)、Orient(方向づけ)、Decide(意思決定)、Act(行動)の頭文字を取った「OODA」そのプロセスを繰り返す「OODAループ」も、今は定番の概念かと思います。
一方で、仮説を元に試行錯誤しながら正解がない「生きた問題」と向き合うためのフレームワークとして知られる、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取った「PDCAサイクル」については、耳にタコができるぐらい「ちゃんと、CheckとActionまでやって、回し続けろ」と言われた経験もあるかと思います。これは、どちらかというと「会議室」の考え方です。
最初に計画を立てる段階で、予測困難なカオスを取り込むことは難しく、一旦「閉鎖系」、つまり「イカ」を海から引き摺り出して「スルメ」に加工してから整理する必要があるからです。
「生きた問題」に対して、最初から「死んだ問題」として向き合ってしまうと、その後のサイクルや検証用の対象データもズレ続けます。その結果、PDCAは最後まで回らず、P(計画)とD(実行)の間を行き来するだけになりがちです。「何も実現しない計画」で「現場」を振り回すのは、「会議室」の得意技ですね。
それに対してOODAループは、まず予測困難な状況、つまり「現場」を観察することから着手します。「こうなるはず」という多少のバイアス、勘や経験は持ち込めるかも知れませんが、優先されるのは「頭の中にある仮説」ではなく、「目の前の事象」です。観察を元に仮説を推し進めるか、改めるべきかを検討します。
これはまさに「現場百遍」のアプローチであり、会議室にこもって小難しく考える暇があるなら、実際に現場へ赴き、足で情報を稼ぐという実践的で泥臭い手法と言えるでしょう。
また、次世代の教育として注目されている科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)の頭文字を取った「STEAM」は、教科書中心の座学一辺倒ではなく、実験やフィールドワークといった実践的な取り組みや、トライアンドエラーを重視している点が特徴です。
これは、従来の受験勉強偏重で「死んだ問題」を解くことに重きを置いた発想から脱却し、複雑で予測困難な「生きた問題」と向き合う力を養おうとするものです。社会に出た後も柔軟に活躍できる素地を鍛えるという点で、OJTに近い「現場」の匂いを感じさせるアプローチと言えるでしょう。
あえて極端な表現を選べば、「高学歴だけど、社会では役に立たない」人材を量産するのではなく、「時代が変化しても、自ら対処できる」人材を増やす方向へと切り替わりつつある、とも言えます。それを実現するためには、従来の詰め込み教育や「死んだ問題」を解く能力も重要ではあるものの、それだけでは不十分だという認識が、先進国に共通する傾向として広がっています。
Wokeや「会議室」はデバフになり得る
Wokeや極端なDEI、移民政策など、リベラルな政策に対して反発や回避が進み、欧米各国で「極右」とされる政党の躍進や、左派的なリーダーの辞任が相次いでいます。この流れを象徴するものとして、トランプ大統領の再任に備えた企業の対応や、「パリ協定」からの離脱や「WHO」脱退といった大統領令も、挙げられるでしょう。
さらに、従来の知的エリートに頼ったところで、アテにならないと露呈したのが、大手コンサルティングファームのリストラや、プロ経営者である「経営コンサルタント業」の倒産増加に現れています。
つまり、過激なWokeが嫌われつつある動きと並行して、リベラル的な価値観や「会議室」的なものからも一定の距離を取ろうという動向が、先進国で顕著になりつつあります。
リベラルが好みそうな理想重視の煌びやかなフレーズや耳慣れない横文字など、かつてはかざすだけで権威の象徴となっていた「印籠」や「バッジ」でも、使い所を誤れば印象や評価を悪化させるリスクを伴う「呪物」となる可能性があります。少なくとも、トランプ大統領が政権を握っている間は、「会議室」の復権は困難だと見ています。
極端な表現かもしれませんが、リベラル的なフレーズは、相手の防御力やスピードなど、ステータスを下げ、弱体化させて戦いを有利に進める魔法やアイテムといった、ゲームでいう「デバフ(debuff)」に近い気がします。それも、デバフ効果が自分たちに及んでしまう「セルフデバフ」でしょう。
例えば、プラスになると思って「実績豊富な(経営)コンサルタントが監修しました」と添えたのに、相手によっては「イマドキ、コンサルタント(笑)」と嘲笑されるかもしれません。そうなると、能力向上といったメリットがないどころか、一方的なデメリットが発生してしまう、まさに「呪いの装備」です。
煌びやかな表現、リベラルや「会議室」を思わせるフレーズを、本当に使っても良いのかどうか。ちょっと立ち止まって、じっくり考えた方が良いのではと個人的には思います。
「現場(カオス)の時代」なら、外へ出ろ
「象牙の塔」や「会議室」にこもり、権威に捏造された幻想や存在しないユートピアを追いかけることも可能です。しかし、牧歌的な農本主義を理想としても、アルカディアは実現されず、ディストピアとして体現されてしまったファシズムや社会主義は、失敗に終わっています。
寺山修司は、『書を捨てよ、町へ出よう』(角川文庫)というタイトルで評論や戯曲、映画を通じて訴えかけました。
さらに、ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロは、「エリートには縦の旅行が足りない」と警鐘を鳴らしています。
最近では、都心部に引きこもり「横の旅行」すら足りていないという指摘もあります。()

その一方で、西洋占星術の世界では「風の時代」や「水瓶座の時代」が到来したとされています。権力や伝統が重んじられた「土の時代」や「社会」や強固な組織を象徴する「山羊座」から、個性やオリジナリティが重視される「風の時代」、「自由」や公平と博愛を重視する「水瓶座」への移行が語られています。
個人的には、この「水瓶座」はタロットカードの大アルカナ「The Fool(愚者)」とも重なるイメージです。「水瓶座」は情報技術に明るく、「理性」や「知性」の象徴ともされていますが、それは机に齧り付いて身につく机上の空論ではなく、旅に出て実践し、他人の知識や自分の経験も活かして検証していくものであり、権威とは無関係で万人に公平です。
「会議室」の人たちから見れば、「愚か者」に見えるかもしれません。しかし、カオスな現実と向き合い、砂埃や汗に塗れながら体力を使って実証する姿は、懸命に働く叩き上げの労働者に重なりませんか?
「閉鎖系」の脳が処理しやすい安定した時代は終わりを迎えました。為替や金利といったダイナミズムや、量子力学のような複雑性こそがリアルであると明らかになった今、「会議室」や「いわゆるリベラル」な物の見方に固執しても、上手くいかないでしょう。
知的エリートの能力も、現場で培われた経験則や直感も、どちらも必要とされる時代です。「綺麗な面だけが良い」という幻想は、もはや通用しません。清濁併せ呑み、「聖」と「俗」を併せ持つ人間として、現実世界と向き合っていきましょう。
キラキラ一辺倒は、気をつけたい
たっぷり文字数を使って、いかにもそれらしい理由も添えてお伝えしてきましたが、偏屈で変わり者のWebサイト制作者として伝えたいのは、「耳障りがいいだけのキレイな言葉」や、「エリートっぽいフレーズ」は控えた方がいいかもしれない、ということ。
どうしてもカッコよく、見栄えの良さを打ち出したい気持ちは分かります。しかし、「キラキラした感じ」や「上流階級っぽい知的かつ高尚な雰囲気」一辺倒だと、むしろ人を遠ざける時代へ突入しているのではないか、と予測しています。
欧米諸国の潮目は変化し、トランプ大統領を意識した保守化が進む中、日本の政治やWeb界隈は周回遅れのトレンドから抜け出せていないように思えたので、複数回に分けてその課題や解決策を提示してきたつもりです。
それを「会議室」と「現場」のフレーズに象徴させ、1998年や2003年に劇場版作品として描いてみせた『踊る』の慧眼さに、密かに恐れ慄いています。側から見ると、そんなフレーズに様々な意味を見出して、2025年にもなってコネクリ回している私の方が、奇妙に映るでしょう。
「現場」で活躍する青島がカッコよく思えたように、誰かに踊らされるのではなく、自ら積極的に『踊』ってみせる。それが、「現場(カオス)の時代」の生き方でしょう。
おしまいに
BBNでは、「現場(カオス)の時代」に合わせた見せ方や伝え方を、毎日追求しています。「会議室」な表現ではなく、「現場」の目が肥えた複雑な人たちに合わせたWebサイト制作や、Webマーケティングに、我々と共に取り組んでみませんか?
少しでも興味があるという方は、ぜひお問い合わせ、ご相談ください。
また、もしこの記事が気に入ったという方は、ぜひ当ニュースレターのフォローやメールアドレスのご登録をよろしくお願いします。
月刊BLUEBNOSEは、毎月1回、第三週の週末に配信予定です。当配信の感想やご質問などございましたら、#BLUEBNOSEか@bluebnoseをつけて、SNSにご投稿いただけますと幸いです。
また、noteやHP上のブログ、Substack等でも情報を発信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
それでは、次回の配信をお楽しみに。
すでに登録済みの方は こちら